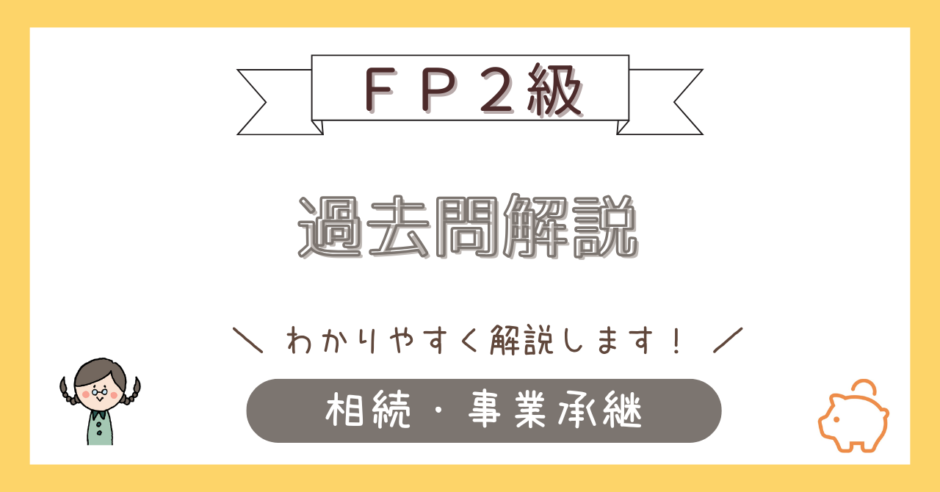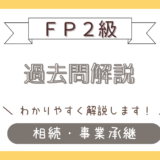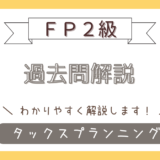FP1級の筆者が、2024年9月のFP2級の学科試験の相続・事業承継を、自分の勉強のために勝手に解説します。
日本FP協会2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2024年9月
【問56】配偶者居住権
正答をタップしてみよう!
民法における配偶者居住権に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していなかった場合であっても、当該建物について配偶者居住権を取得することができる。
1:誤り(正答)
配偶者居住権とは、夫や妻名義の住宅に住んでいる配偶者が、名義人が亡くなった後もその住宅に住み続けることができる権利です。
配偶者居住権は、平成30年の民法改正で新たに創設され、令和2年4月から施行されています。遺産分割の際、配偶者が住宅の所有権を取得するよりも低い金額で「居住権」を取得できるようにすることで、配偶者が住まいと生活資金の両方を手に入れやすくなりました。高齢化が進む中で、夫婦の一方が亡くなった後も、残された配偶者が長期間生活するケースが増えていることが背景にあります。
配偶者居住権が成立するためには、次の2つの条件を満たす必要があります。(民法第1028条)
・配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいること
・配偶者が配偶者居住権を取得する内容の、遺産分割、遺贈、死因贈与が行われること
このように、配偶者居住権が成立するには、配偶者が相続開始時にその住宅に住んでいる必要があります。したがって、この選択肢は誤りとなります。
(配偶者居住権)
第1028条第1項 被相続人の配偶者(中略)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(中略)の全部について無償で使用及び収益をする権利(中略)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2.被相続人の財産に属した建物について、被相続人が相続開始の時に被相続人の配偶者以外の者と共有していた場合、被相続人の配偶者は、当該建物について配偶者居住権を取得することができない。
2:正しい(✖)
問題文のとおりです。民法第1028条第1項の但し書きの内容になります。
配偶者居住権は、配偶者が無償で建物の全部を使用できる非常に強力な権利です。
そのため、もし他の人と建物を共有している場合にまで配偶者居住権が適用されると、その共有者の権利を害してしまう可能性があります。
そのため、他の人と共有している建物については、配偶者居住権を設定することができません。
(配偶者居住権)
第1028条第1項 被相続人の配偶者(中略)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(中略)の全部について無償で使用及び収益をする権利(中略)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
3.配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者居住権の目的となっている建物の所有者の承諾を得たうえで、第三者に当該建物の使用または収益をさせることができる。
3:正しい(✖)
問題文のとおりです。民法第1032条第3項の内容になります。
(配偶者による使用及び収益)
第1032条第3項 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4.配偶者居住権の目的となる建物の全部が滅失して使用および収益をすることができなくなった場合、配偶者居住権は消滅する。
4:正しい(✖)
問題文のとおりです。配偶者居住権は以下の場合に消滅します。
・期間満了
・配偶者の死亡
・建物の全部滅失等
・建物が配偶者の所有物になる
・所有者からの消滅請求(善管注意義務違反、無許可の転貸などのルール違反があった場合)
・配偶者による権利の放棄
【問57】相続税の配偶者の税額軽減
正答をタップしてみよう!
配偶者に対する相続税額の軽減(以下「配偶者の税額軽減」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.配偶者の税額軽減の適用を受けた配偶者が相続または遺贈により取得した正味の遺産額が1億6,000万円を超える場合は、その遺産額が配偶者の法定相続分相当額以下であっても、配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)とならない。
1:誤り(✖)
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続や遺贈で取得した正味の遺産額について、次のいずれか多い方の金額ま、配偶者に相続税がかからないという制度です。
(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
この制度では「1億6,000万円」という金額が目立ちますが、資産家などの相続では(2)が重要です。
特に、配偶者が唯一の相続人であるケースでは、配偶者が全財産を取得しても相続税の負担がないことを意味します。
したがって、この選択肢では「配偶者の相続税額は0(ゼロ)になる」でなければならないので、誤りです。
2.配偶者の税額軽減の適用を受け、納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
2:誤り(✖)
配偶者の税額軽減を適用するには、相続税の申告書に明細書を添付して提出する必要があります。
申告書を提出しなければ、たとえ税額軽減の適用によって最終的に納付すべき相続税額が0円になったとしても、その軽減措置を受けることはできません。
つまり、相続税が0円となるケースでも、相続税の申告書を提出することが必要です。
3.相続の放棄をした配偶者は、配偶者の税額軽減の適用を受けることができない。
3:誤り(✖)
相続を放棄した配偶者でも、配偶者の税額軽減を適用することができます。
相続放棄をした配偶者に遺贈によって取得した財産があれば、その財産に対して適用することが可能です。
(相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減)
19の2-3 配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、配偶者が相続を放棄した場合であっても当該配偶者が遺贈(中略)により取得した財産があるときは、適用があるのであるから留意する。
4.配偶者の税額軽減の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をしている者に限られる。
4:正しい(正答)
問題文のとおりです。配偶者の税額軽減は、法律上の婚姻が成立している者にのみ適用されます。したがって、事実婚や内縁関係の者には、この制度は適用されません。
(内縁関係にある者)
19の2-2 法第19条の2第1項に規定する配偶者は、婚姻の届出をした者に限るものとする。したがって、事実上婚姻関係と同様の事情にある者であっても婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者は、当該配偶者には該当しないのであるから留意する。
【問58】金融資産の相続税評価
正答をタップしてみよう!
金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.普通預金の価額は、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、課税時期現在の預入高によって評価する。
1:正しい(✖)
預貯金の相続税評価額は、預入高と既経過利子の額(源泉徴収後の額)との合計となります。しかし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、既経過利子の額が少額なものに限り、預入高のみで評価することとされています。(財産評価基本通達203)
したがって、選択肢の内容は正しいです。
2.外貨預金の邦貨換算は、原則として、取引金融機関が公表するその外貨預金の預入時における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
2:誤り(正答)
この選択肢は、一見すると邦貨換算の問題に見えますが、実は財産評価の基準日に関する問題です。
外貨預金を日本円に換算する際に使用する為替相場は、「預入時」のものではなく、「課税時期(相続の場合は相続開始時)」の最終の為替相場を用いる必要があります。「対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場」を用いる点は正しいです。(財産評価通達4-3)
外貨建ての債務(マイナスの財産)を日本円に換算する場合は、対顧客直物電信売相場(TTS)を使用します。
3.金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と課税時期において利払期が到来していない利息のうち源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
3:正しい(✖)
問題文のとおりです。
ちなみに利付公社債の評価方法は、上場している場合、上場しておらず日本証券業協会の「店頭売買参考統計値」がある場合、それ以外の3パターンに分かれています。
| 上場している | 課税時期の最終価格+既経過利息の額(源泉徴収後) |
| 上場しておらず「店頭売買参考統計値」がある | 課税時期の平均値+既経過利息の額(源泉徴収後) |
| それ以外 | 発行価額+既経過利息の額(源泉徴収後) |
4.相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約(解約返戻金等のないものを除く)に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。
4:正しい(✖)
問題文のとおりです。
被相続人が保険料を負担していた生命保険契約のうち、保険事故がまだ発生しておらず、解約すると解約返戻金が支払われる保険(掛け捨てでない保険)については、その解約返戻金相当額が相続財産として扱われます。
例えば、妻を被保険者とする生命保険の保険料を夫が支払っていて、妻よりも先に夫が亡くなったとすると、その保険を相続開始時に解約した場合の解約返戻金の額が、夫の相続財産として扱われます。
解約返戻金相当額を相続する(あるいは相続したとみなされる)のは、その保険の契約者です。
もし契約者が被相続人(亡くなった本人)であれば、その契約者の地位を引き継いだ人が相続したものとして扱われます。
【注意点】
・実際に解約して解約返戻金を受け取ったかどうかに関係なく、課税対象になります。
・死亡保険金とは異なり、非課税枠(500万円×相続人の数)は適用されません。
【問59】遺言
正答をタップしてみよう!
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.共同相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は無効となる。
1:誤り(✖)
たとえ遺留分を侵害する内容であっても、その遺言が無効となるわけではありません。
遺言は、故人の意思を尊重することを目的としているため、形式面においては厳しい要件がありますが、内容についてはよほどのことがない限り有効とされます。
したがって、遺留分を侵害する場合でも、遺言自体は無効とはなりません。
【遺言が無効になる主な原因】
・遺言者に意思能力がなかった
・公序良俗に反する内容だった
・遺言の方式に間違いがあった
・2人以上の者による遺言だった
・遺言者の後見人等が利益を受ける内容だった
・受贈者が先に亡くなった
・目的物が遺言者の相続財産でなかった
など
仮に全財産を知人に遺贈するという内容でも、遺言書としては有効です。一方、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求で、相続人としての最低限の権利を守ることができます。
2.共同相続人のうち一部の者についてのみ相続分を指定する内容の遺言は無効となる。
2:誤り(✖)
相続分を指定する遺贈(包括遺贈)をする場合、一部の者のみを対象とすることが可能かという問いのようです。
そのような遺言が無効になるルールはないため、選択肢は誤りといえます。
関連する条文としては、遺言者の自由な遺産の処分を保障する、民法第964条になるでしょうか。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
3.被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
3:正しい(正答)
問題文のとおりです。民法の条文どおりの内容になります。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
4.遺言執行者を指定する内容の遺言は無効となる。
4:誤り(✖)
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選ばれる者をいいます。
遺言執行者は、遺言によって指定することが可能です。
指定がない場合でも、利害関係人の請求によって家庭裁判所に選任してもらうことができます。
遺言執行者を遺言で指定することは法律で認められていますので、この選択肢の内容は誤りです。
(遺言執行者の指定)
第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
【問60】M&A
正答をタップしてみよう!
M&Aに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.事業譲渡によるM&Aでは、譲受け側の会社は、個別に同意した範囲で特定の事業・財産のみを譲り受けるため、一般に、簿外債務や偶発債務リスクを遮断しやすい。
1:正しい(✖)
事業譲渡とは、事業の全部または一部を売却するM&Aの手法の一つです。
事業譲渡によるM&Aには、その事業に属する資産や負債、雇用契約などを一つ一つ、債権者や従業員の同意などを得ながら譲り受け側(買い手)に引き継がなければならないため、手続きが煩雑になるという特徴があります。また、許認可は引き継げないことが多く、その場合は買い手が新たに申請しなければなりません。
一方、特定の事業や財産を引き渡す手法であるため、買い手にとっては、簿外債務・偶発債務のリスクを遮断しやすいメリットがあります。
したがって、選択肢の内容は正しいです。
譲り渡す側(売り手)にも、個別の事業ごとに売却できるため、事業の一部を手元に残すなど柔軟な選択ができるメリットがあります。
2.株式譲渡によるM&Aでは、譲渡し側の法人格に変動はなく、会社の資産、負債、従業員や社外の第三者との契約、許認可等は、原則として存続する。
2:正しい(✖)
株式譲渡とは、譲り渡し側(売り手)の株主が保有する発行済株式を、譲り受け側(買い手)に売却するM&Aの手法です。
イメージとしては、会社のオーナー(株主)が変わるだけで、会社はそのまま残ります。そのため、会社の資産、負債、契約、許認可等も原則存続します。
したがって、選択肢の内容は正しいです。
事業譲渡のように資産や負債などを一つ一つ確認しながら引き継ぐ手間がかからないため、比較的簡便な手法になります。一方で、帳簿に現れない「簿外債務」や、表面化していないだけのさまざまな問題を包括的に引き受けるリスクがあることに注意が必要です。
3.会社が事業の全部の譲渡や事業の重要な一部の譲渡を行う場合、その行為に係る契約について、原則として、株主総会の決議による承認は不要である。
3:誤り(正答)
会社が、自社の事業の全部の譲渡や事業の重要な一部の譲渡を行う場合、効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議による承認を得ることが原則として必要になります。
譲渡側の企業(売り手)の株主にとって、影響が大きい取り引きだからです。
したがって、「原則として不要」とする選択肢の内容は、誤りになります。
(事業譲渡等の承認等)
第467条第1項 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(中略)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一 事業の全部の譲渡
二 事業の重要な一部の譲渡(中略)
(以下省略)
参考までに、買い手が売り手の特別支配会社(議決権の90%以上を保有している会社)である場合は、株主総会の承認を必要としないという例外もあります。
譲渡側の企業(売り手)の株主がほぼ買い手であり承認されることが確実なので、手続きを簡略化するための規定になります。
(事業譲渡等の承認を要しない場合)
第468条第1項 前条の規定は、(中略)契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(中略)である場合には、適用しない。
4.事業譲渡によるM&Aにより事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内において、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。
4:正しい(✖)
M&A後の買い手の利益を保護するため、譲渡企業(売り手)は譲渡した日から20年間、近隣区域で同じ事業を行うことが禁じられています。会社法の条文どおりの内容です。したがって、正しい選択肢になります。
(譲渡会社の競業の禁止)
第21条 事業を譲渡した会社(中略)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(中略)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。