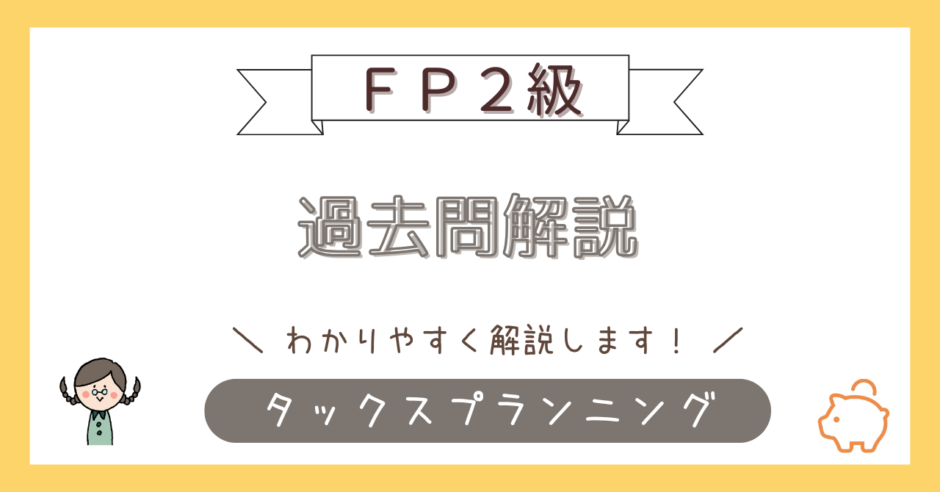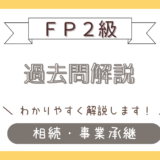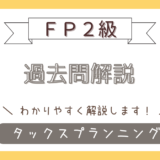FP1級の筆者が、2024年9月のFP2級の学科試験のタックスプランニングを勝手に解説します。
日本FP協会2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2024年9月
【問31】日本の税制
正答をタップしてみよう!
わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額の多寡にかかわらず、税率が一律となる比例税率が採用されている。
1:誤り(✖)
所得税の税率は「比例税率」ではなく、5%~45%の「超過累進税率」が採用されています。
| 課税総所得金額 | 適用税率 |
|---|---|
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円以上330万円未満 | 10% |
| 330万円以上695万円未満 | 20% |
| 695万円以上900万円未満 | 23% |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
超過累進税率とは、一定額を超えた所得部分(超過部分のみ)に対し、段階的に高い税率が適用される仕組みです。
例えば、課税総所得金額が4,000万円ちょうどの場合、「4,000万円×45%=1,800万円」ではなく、「195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+・・・(4,000万円-1,800万円)×40%」で13,204,000円です。
これを簡単に計算できるようにしたものが、試験の問題文で与えられる下記の「速算表」になります。
| 課税総所得金額 | 適用税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
速算表でも同じ結果になります。【例】4,000万円×45%-4,796,000円=13,204,000円
2.贈与税では、納税者が申告書に記載した財産の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
2:誤り(✖)
贈与税のように、納税者自身が課税対象となる金額や納税額を計算し、申告・納税を行う仕組みを「申告納税方式」といいます。
これに対し、行政機関が税額を計算し、納税者に通知する課税方式は「賦課課税方式」といいます。
【申告納税方式の例】
所得税、法人税、消費税、贈与税、相続税
法人事業税、法人都民税、法人道府県民税、法人市町村民税 など
【賦課課税方式の例】
加算税
固定資産税、不動産取得税、自動車税など
3.法人税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。
3:正しい(正答)
「直接税」は、納税義務者と税の負担者が同じである税です。反対に、「間接税」は、納税義務者と税の負担者が異なる税を指します。
たとえば、法人税は法人が自ら所得の一部を納税するため、直接税に分類されます。
一方で、消費税は消費者が支払った税を事業者が一時的に預かり、まとめて納税する仕組みになっているため、間接税となります。
4.不動産取得税および登録免許税は、いずれも地方税に該当する。
4:誤り(✖)
不動産取得税は、都道府県が課税主体となる「地方税」です。一方で、登録免許税は「国税」に分類されます。
・不動産取得税・・・不動産を新たに取得したり、増改築した際に、不動産の所有者に対して課される税です。
・登録免許税・・・不動産登記などの申請時に支払う税です。
国税の例
・所得税、法人税、地方法人税、消費税、贈与税、相続税、登録免許税、印紙税、自動車重量税など
地方税の例
・事業税、住民税、地方消費税、固定資産税、不動産取得税、自動車税など
【問32】所得税の各種所得の計算
正答をタップしてみよう!
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人が賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
1:正しい(✖)
個人が賃貸している土地を売却した場合、その売却益は譲渡所得として扱われます。選択肢は正しいです。
不動産の販売業を営む個人が、販売目的で仕入れた土地を売却したのであれば、事業所得になります。今回の選択肢には「賃貸している土地」と記述されているため、販売用に仕入れた土地ではないと解釈する必要があります。
2.個人が不動産の貸付けを事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得となる。
2:正しい(✖)
個人が不動産の賃貸を事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得になります。選択肢は正しいです。
なお、賃貸が事業的規模でなくても不動産所得であることには変わりません。事業所得と混同させるための引っかけです。
3.個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。
3:正しい(✖)
個人年金保険から支払われる年金に課される税は、保険料負担者が誰であるかによって変わります。
| 保険料負担者 | 税目 |
|---|---|
| 本人 | 所得税 |
| 本人以外 | 贈与税 |
選択肢は、年金の受取人本人が保険料負担者であるため所得税の対象になります。
続いて、年金契約から支払われた所得の種類は、受け取り方法によって異なります。
| 受け取り方法 | 所得の種類 |
|---|---|
| 年金 | 雑所得 |
| 一時金 | 一時所得 |
選択肢は、年金形式で受け取っているため、その年金収入は雑所得になります。
したがって、選択肢は正しいです。
4.個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
4:誤り(正答)
株主が受け取る剰余金の配当は、「配当所得」になります。
株式を購入した元手がたとえ個人事業の資金であっても、その所得区分には影響がなく、事業所得とはなりません。そのため、事業所得とするこの選択肢は誤りです。
【問33】所得税の総所得金額の計算
正答をタップしてみよう!
Aさんの2024年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。
なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
・給与所得の金額 600万円
・不動産所得の金額 ▲50万円(土地等の取得に要した負債の利子の額はない)
・譲渡所得の金額 ▲180万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
1.370万円
1:誤り(✖)
2.420万円
2:誤り(✖)
3.550万円
3:正しい(正答)
所得税の計算において、その年の不動産・事業・譲渡(総合課税)・山林所得で生じた損失は、一定の手順に従って、他の黒字所得と損益通算(相殺)します。
・給与所得の金額 600万円
・不動産所得の金額 ▲50万円(土地等の取得に要した負債の利子の額はない)
・譲渡所得の金額 ▲180万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
不動産所得の▲50万円を給与所得600万円と損益通算します。
給与所得600万円+不動産所得▲50万円=550万円
まずは不動産所得や事業所得の損失を、利子、配当、給与、雑所得と通算します。
この時、不動産所得の必要経費に土地等を購入するための借入金の利子があれば、その利子の金額は、損益通算する損失の金額から外さなければなりません。
続いて、譲渡所得の損失を損益通算します。
譲渡所得の▲180万円は「ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失」ですので、この▲180万円を他の所得と損益通算することはできません。
生活に通常必要でない資産から生じた損失は、損益通算の対象にならないからです。
550万円+譲渡所得▲0万円=550万円
したがって、「550万円」が正解になります。
【もしも損益通算が可能な損失だったら・・・?】
もし譲渡所得の損失が損益通算ができるものだった場合、その年の黒字所得に一時所得があれば、先に一時所得と損益通算をします。通算しきれない、残った損失があれば手順1の黒字と通算します。
今回は一時所得がないため、▲180万円をそのまま、手順1の550万円と通算した金額が答えになります。
また、不動産所得には「土地等の取得に要した負債の利子」の他にも損益通算できない損失が存在します。
特に、国外中古不動産の償却費による損失は令和3年から損益通算の対象外となっており、海外不動産投資を検討する方にとって重要な改正です。
4.600万円
4:誤り(✖)
【問34】住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
正答をタップしてみよう!
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2024年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。
1.住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
1:正しい(✖)
住宅ローン控除を受けるためには、控除を申請する人(住宅の所有者)と控除の対象となる住宅の両方に適用要件があります。
控除を受ける人の要件としては、次の3つのポイントを覚えておくと良いでしょう。
・住宅を取得した日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること
・その年の12月31日まで引き続き居住していること
・その年の合計所得金額が一定額以下であること
したがって、選択肢は正しいです。
なお、その年の12月31日まで引き続き居住していることや、合計所得金額が一定額以下であることについては、住宅ローン控除期間中、毎年判定しなければなりません。
2.住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
2:誤り(正答)
住宅ローン控除の適用を受ける者には、その年の合計所得金額に上限があります。
この所得上限は近年改正され、次のようになっています。
・2021年以前:3,000万円以下
・2022年以降:2,000万円以下
問題文は2024年中に入居するケースのため、2024年のルールが適用されます。
したがって、所得上限は3,000万円ではなく2,000万円以下となり、選択肢は誤りです。
なお、住宅ローン控除の適用要件は「入居した年のルール」が控除期間中ずっと適用されます。そのため、2021年以前に入居した方の所得上限は、現在も「3,000万円以下」になります。
3.住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
3:正しい(✖)
住宅ローン控除は、住宅ローンの返済期間が「10年以上」である必要があります。
繰り上げ返済により、控除を受けている途中で返済期間が短くなった場合は、住宅ローンを最初に返済した月から、繰り上げ返済後の最後の返済予定月までの期間が「10年以上」であるかどうかで判定します。
もし繰り上げ返済によって返済期間が「10年未満」となった場合、その年から住宅ローン控除が受られなくなります。
したがって、選択肢は正しいです。
4.新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住の用に供していた住宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
4:正しい(✖)
住宅ローン控除を受けるには、住宅に入居した年・その前年・その前々年の所得税について、次の特例のいずれかを適用していないことが条件となります。
・居住用財産の譲渡所得の特別控除(マイホーム特例)
・居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例
・居住用財産の長期譲渡所得の買い換え特例
・居住用財産の長期譲渡所得の交換特例
・既成市街地等内にある土地等の買い換え及び交換の特例
したがって、選択肢は正しいです。
【問35】給与所得者の確定申告の要否
正答をタップしてみよう!
給与所得者の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
1.A社からの給与の収入金額が3,000万円で、B社からの原稿料収入に係る雑所得の金額が15万円ある場合、確定申告は不要である。
1:誤り(✖)
給与を1か所から受けており、その給与が源泉徴収の対象となっている場合、「給与所得および退職所得以外の所得の合計」が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
選択肢の場合、「給与所得および退職所得以外の所得の合計」は15万円で確定申告不要となる条件を満たしていますが、A社からの給与収入が2,000万円を超えているため、この給与は年末調整が行われていません。
したがって、このケースは確定申告が必要であり、選択肢は誤りとなります。
2.C社からの給与の収入金額が800万円で、アルバイトとして兼業しているD社からの給与の収入金額が30万円ある場合、確定申告は不要である。
2:誤り(✖)
2か所以上から給与を受け取っている場合、年末調整を受けていない給与(選択肢の場合、D社の30万円)の収入金額と給与および退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。
ただし、年末調整を受けていない給与については「収入金額」で判定するため、「30万円>20万円」となり、確定申告が必要です。そのため、選択肢は誤りとなります。
3.E社からの給与の収入金額が800万円で、生命保険の満期保険金に係る一時所得の金額が50万円ある場合、確定申告は不要である。
3:誤り(✖)
給与を1か所から受け取り、かつ、その給与が源泉徴収の対象である場合、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
ここで、「給与所得および退職所得以外の所得」が「一時所得」の場合には、まずその金額が「収入」か「所得」かを確認しましょう。
選択肢で与えられているのは「一時所得の金額」ですので収入ではなく所得なのですが、もしこれが収入であれば、次の計算式で所得を計算します。
【一時所得の計算式】
収入-収入を得るために支出した額- 特別控除額(最高50万円)
問題文を見るに、おそらく収入と所得の引っかけではないかと思います。
なお、一時所得は総所得金額に算入する際、上記の計算額にさらに2分の1を乗じます。
そして、給与所得者の確定申告の要否を判断する「20万円以下」については、一時所得に2分の1を乗じた金額で行います。
したがって、「25万円(50万円×2分の1)>20万円」となり、確定申告は必要なので選択肢は誤りとなります。
「給与所得及び退職所得以外の所得」とは、総所得金額や退職所得等の合計から給与所得及び退職所得を控除した金額です。そのため、20万円以下の判定も総所得金額で行う必要があるのです。(所得税法基本通達121-6)
4.F社からの給与の収入金額が70万円で、老齢基礎年金および老齢厚生年金の公的年金に係る雑所得の金額が250万円ある場合、確定申告は不要である。
4:正しい(正答)
年金受給者の場合、源泉徴収を受けている年金収入が400万円以下であり、それ以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
ただし、この選択肢で与えられているのは「給与の収入金額が70万円」、「公的年金に係る雑所得の金額が250万円」なので、判定に必要なものが逆になっています。
そのため、「所得」と「収入」をそれぞれ逆にする必要があります。
まず、給与については、金額が多くないため、最低控除額(55万円)が適用されます。したがって、給与所得は15万円です。
続いて、年金については、仮に年金収入が400万円である場合で雑所得を計算してみると、その額は272.5万円となります。この結果から、「雑所得の金額が250万円」の年金収入は400万円以下であることがわかります。
したがって、確定申告は不要であるため、この選択肢は正しいです。
しかし、この解き方だと公的年金等控除の速算表を暗記していなければ解けません。この問いだけ、もの凄くハードですよね・・・