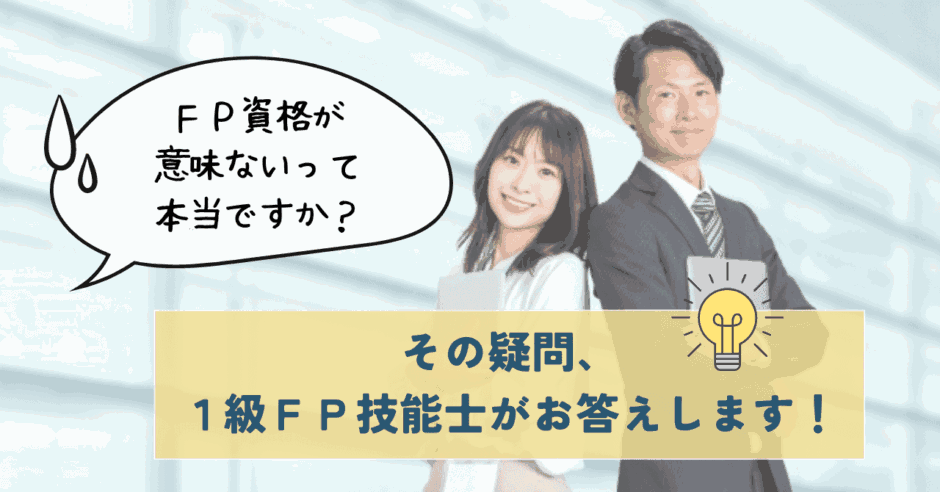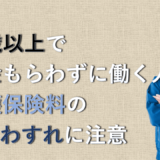FP(ファイナンシャルプランナー)とは、誰にとっても身近な個人のお金の話を学問として体系化した資格です。
しかし、世の中にお金の知識がまったくない人はいません。
例えば、大きな買い物をしてローンを組んだり、社会保険や税金のことをインターネットで調べてみたり、友達から投資について話を聞いたりした経験は誰にでもあると思います。
身近な問題であるが故に「わざわざ専門的に勉強をする意味はないのではないか」「仕事ではどうせ役に立たないだろう」と考えて、受験を迷っている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、FP3級からFP1級まで取得してみたフリーライターの筆者が考える、なぜFP資格は意味がないと言われるのか、FP資格を役立てられる人の特徴とその理由、FP資格でなくてもいいケースなどをお伝えします。
FP資格は意味がない・役に立たないと言われる理由
理由1:独占業務がないので独立しにくい
世の中には「士業」、いわゆる「サムライ業」とよばれる専門家がいます。
弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士などです。
これらの士業には、資格がなければやってはいけないという「独占業務」がそれぞれにあります。
そして、これらの独占業務は、企業活動に附随して発生するものが多いため、これらの試験に合格をすれば、企業を相手に独立の道が見えてきます。
しかし、FPに独占業務はありません。FP1級から3級は「〇級FP技能士」として「士」の文字こそ付いているものの、FPの業務について定めた法律はなく、そのため独占業務もないのです。
独立できることを期待してFPについて調べた人からすれば、「FPは(独立するにあたって)役に立たない資格」という印象になってしまいます。
理由2:どうやって稼ぐのかいまいちよくわからない
独占業務がなくても独立することは可能です。
FPの場合は一般的に、保険販売(保険代理店業)、執筆業、セミナー講師、そして個人向けのコンサルティング業で稼ぐことができると言われています。
しかし、これらはFPだけの業務というわけではありませんから、さまざまな業界との競争になります。
また、保険販売・執筆業・セミナー講師については基本的に売り切り型のビジネスであり、稼ぐには顧客獲得のための営業をし続けなければなりません。不得意な人にはかなりの努力が求められます。
理想は、個人向けのコンサルティングです。月額のコンサルティング契約を締結することによって安定した収入が期待できます。将来に不安を感じ、「一度、お金のプロに相談してみたい」という人はたくさんいるはずです。
しかし、コンサル契約を必要とするお客さんは、基本的には自分だけで運用方法を考えきれない収入や資産がある人に限られます。多くの人は月額料金を支払ってまでFPに継続的にアドバイスを受けたいとは思っていません。
そして、こうした収入や資産のある人には、すでに他の専門家がついていることが多いです。
たとえば会社の経営者なら、融資を通じてつきあいをしている銀行、税務相談や確定申告を通じて顧問契約をした税理士事務所といったお金のプロがついています。
こうした専門家は、経営状態から家族構成まで把握して継続的な支援をしていることがほとんどです。
FP資格1つのみで、金融のプロや財務・税務のプロと戦っていくことは至難の業といえるでしょう。
安定して稼げるビジネスが少なく常に他の業界とも戦わなければならないことなどから、「いまいち稼ぐ方法がよくわからない資格」とされ「意味がない・役に立たない」と言われることがあります。
FP資格は何のためにあるのか
FP資格は役に立たない・意味がないと言われることのある資格ですが、そもそも独立したくてFP資格を取る人はおそらく少数派です。
FPに独占業務がないことは、FP試験を勉強した人が一番よく知っています。そういう問題が出題されるからです。
それでは、FP資格はいったい何のためにあるのでしょうか。
筆者が知る限り、FPの受験者は、自分のマネーリテラシーの向上のためであったり、自分の知識レベルを示すためであったり、他の資格やこれまでの職歴にFP資格を追加するためであったりと、自分の成長やブランディングを目的としています。
自分の将来を戦略的に考えられる人やお金の勉強をする意味を自分で見つけられる人にとっては、FPが独立できる資格か、他の専門家などと戦える資格かどうかはまったく問題になりません。
FP資格を役立てられる人の特徴
FP資格を取得することによって、今の生活や仕事のレベルアップに役立てられる場合があります。
FP資格を生活や仕事のレベルアップに役立てられる人は、下記のような人です。
・家計を管理している
・仕事でお金の相談にのる機会がある
・転職を考えている
・起業してみたい
・働きながら税理士や社労士などの資格取得を目指している
・副業でお金の情報発信をしてみたい
なぜ、こうした人たちにFP資格が役に立つのか、その理由を一つずつ解説します。
家計を管理している
家計を守ることに専門知識がいるのかと思われるかもしれませんが、家計を守ることは小さな会社を守ることと同じです。
もし年100万円あれば、小さな会社ならパートさんを1人雇うなど色々な課題を解決することができます。
ところが家計の年100万円になると、いつの間にか色々な支払いで減ってしまい、後からそれに気が付いてビックリしたことはないでしょうか。
なぜうまく切り分けて貯蓄や投資に回せなかったのか、原因がよくわからないことも多いと思います。
これは、生活のための支出や将来のための支出の全体像がうまく把握できていないことが原因の一つです。
このままでは教育や老後のための目標金額を達成できないことになりかねません。
家計管理のスキルアップにおすすめなのは、日本FP協会の3級の実技試験にでてくる「家計のキャッシュフロー」の問題です。
家計のキャッシュフローの問題とは、将来の収入と生活費を予測して一覧表にし、資金計画の問題点を見つけたりその解決策を考えたりする問題です。お金の考え方や資金計画の立て方に対する一生もののスキルが手に入ります。
具体的には下記のような問題になります。

(画像出典)日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定実技試験(資産設計提案業務)2023年9月より
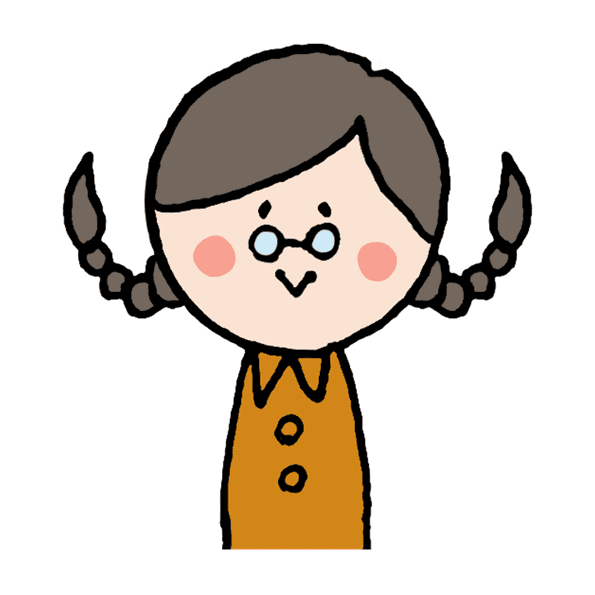
家計のキャッシュフローは「ライフプランニング」という分野の問題です。
FP試験には全部で6つの分野があり、これ以外にも、税金の控除の種類、社会保険でカバーできる範囲、老齢年金や遺族年金の受給要件など、知らなければ損をする可能性がある知識を網羅的に学ぶことができます。
・ライフプランニング
・リスクマネジメント(社会保険や保険商品)
・金融資産の運用
・タックスプランニング(税金)
・不動産
・相続・事業承継
仕事でお金の相談にのる機会がある
営業担当や顧客対応をする仕事では、お金に関する一般常識がないと相手から信頼されないことがあります。
筆者がそうでした。法人税の勉強してお金のプロの顔で顧問先企業を訪問したのに、話題が得意でない分野、たとえば年金の受給に関することなどに逸れるととたんに話せなくなり、相手のほうが詳しくて落ち込むのです。
FP試験は、ライフプランニング、社会保険や保険商品、金融資産運用、税金、不動産、相続の6分野から出題されます。
世間では常識なのに自分にはない知識が何なのか、きちんとあぶり出して教えてくれます。
そして2級、1級と進むうちにそれまで関心のなかった情報を広くキャッチできるようになり、だんだんと自分のほうが相手よりも知識があるケースに出合うことが多くなっていきます。
対人の仕事が好きな人は、目の人を喜ばせることが好きだったり貢献意識が高かったりする人が多いと思います。
FP試験の勉強中でも、教科書を読みながら「あのお客さんに教えてあげたいな」とか「この話はこういう商談の場面で使えそう」という発見やアイデアの連続になり、楽しく学習できると思います。
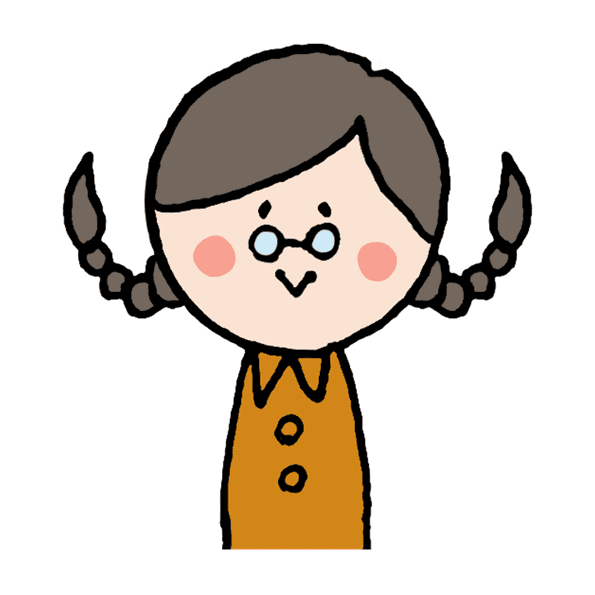
筆者のおすすめは、FP試験で学べる保険商品の知識です。特に実技試験で出題される、本契約と特約内容から保障範囲と金額を読み取る問題は、保険販売員の登録試験よりかなり実戦的になっています。
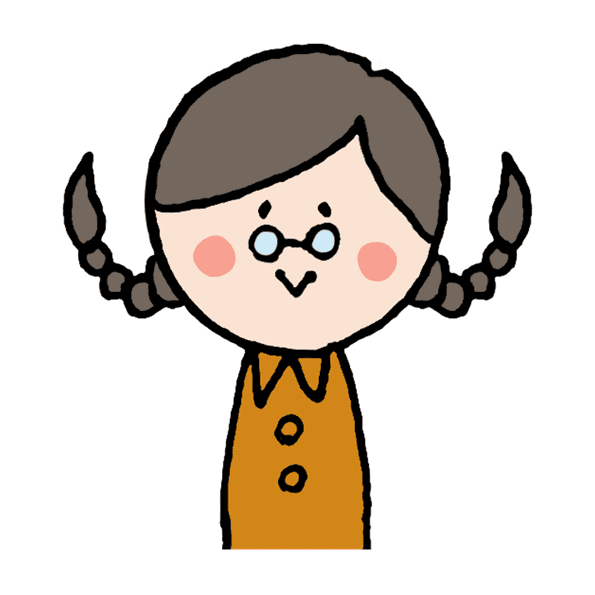
保険の総合代理店などで販売をしている人がFP試験を勉強すると、お客さま目線で商品説明ができるようになるため、信頼される保険営業ができるようになると思います。
転職を考えている
保険業界、不動産業界、相続業界などではFP資格取得者が優遇される場合があり、中にはFPに資格手当をつけている求人もあります。
FPは人気資格であり知名度も高いため、転職を考えている場合は取得しておいて損はありません。
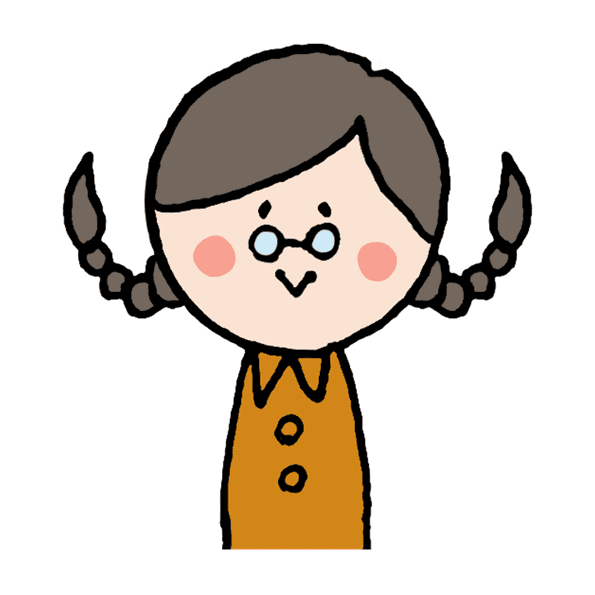
資格手当があるのは、保険代理店業を手掛ける会社が多いようです。転職サイトなどに「FP」のワードで検索をかけてみるとわかりやすいですよ。企業コンサルなどの業界にも歓迎されます。
起業してみたい
自分のスキルを活かして起業することを考えている人にも、FP資格はおすすめです。
会社員であれば老後の資産形成は、退職金や厚生年金によって何とでもなりますが、独立する人は、老後の生活についてすべて自己責任で考えなければなりません。
また、個人で独立すると、社会保険の面で会社員よりも不利な扱いを受けたり、会社が計算してくれていた税金を自分で計算して納めなければならないなど、お金にかかわるさまざまな変化があります。
起業してから後悔することのないよう、事前にお金の勉強をしておくことは欠かせません。
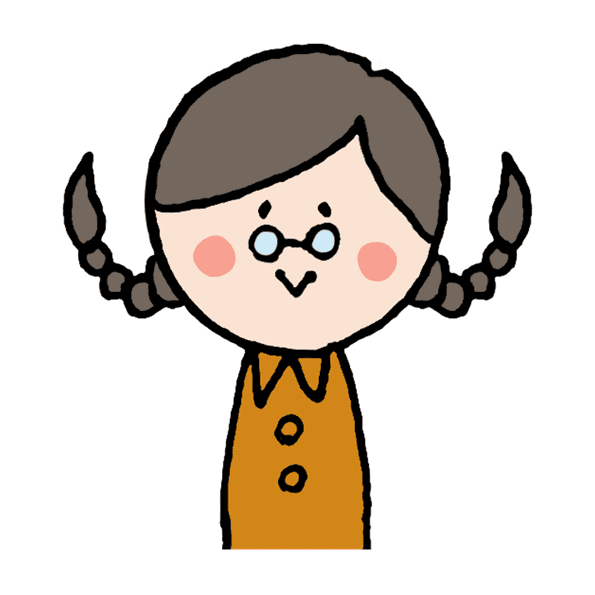
FPの勉強をすることによって「今、会社をやめるともったいないかも…」ということに気づくこともあるでしょう。それはそれで、長い人生においてプラスの発見になるはずです。
他士業の資格を目指している
税理士や社会保険労務士といった難関の士業資格は1,000時間以上の勉強を要します。
こうした難関資格を目指す場合、合格までに何年もかかることがめずらしくありません。働きながらであれば、10年以上かかることもあります。
こうした難関資格を目指す人は、試験範囲が重複しており知名度もあるFPから先に腕試しで受けてみるのもよいでしょう。
初学者よりも大幅に学習時間を抑えることができるはずですし、FP試験は年に3回(5月・9月・1月)開催されるため、他の資格勉強と並行して取り組みやすいといえます。
さらに、税理士・社労士・中小企業診断士といった、中小企業の経営に関わる専門家を目指す場合は、FPとのダブルライセンスによるブランディングに活用することがおすすめです。
中小企業にとって会社は社長個人の財産でもあるため、会社の相談にのることは、経営者個人の資産に関する相談に乗ることと切り離せない部分が存在します。社長と信頼関係を築き長くつき合っていくためにも、保険商品や金融商品の話、将来の相続や事業承継の話など、さまざまな相談に柔軟に対応できる知識が必要です。
つまり、企業活動に対する専門資格とFP資格は、実はかなり相性が良い資格であるといえます。
このような相性の良さがあるため、FP資格を取得することは、士業事務所やコンサル会社への転職時のPRや独立時のブランディングにも役立ちます。
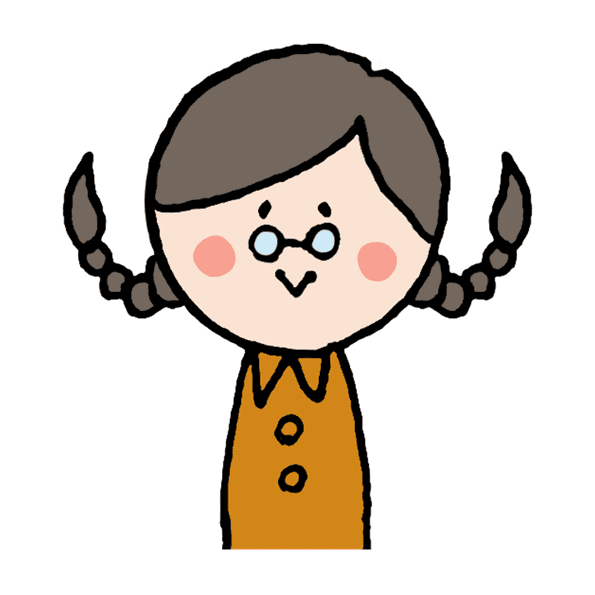
FP試験の勉強は物足りないかもしれません。その場合は、勉強中の資格試験で学べない分野に力を入れてみると良いと思います。例えば、会計事務所で働きながら税理士試験の勉強をしている場合、実務では社会保険の知識も必要になります。しかし、これを最初から社労士のテキストでキャッチアップしようとすると詳しすぎて実務への落とし込みが難しく、資格勉強の支障にもなります。
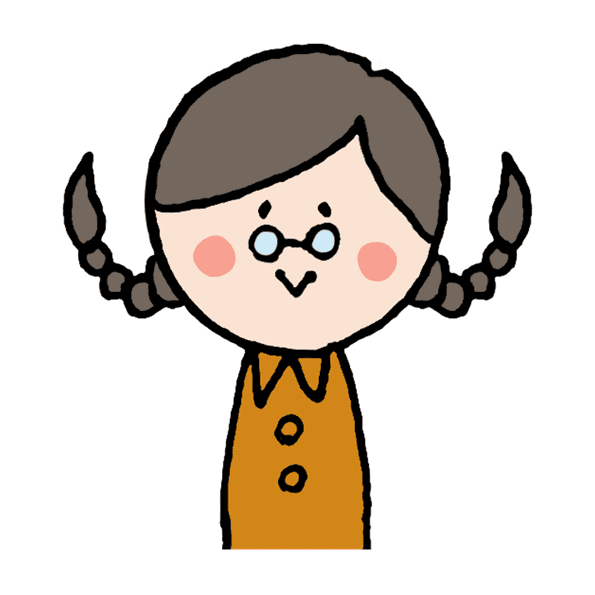
FP試験なら、年金や健康保険の保障範囲など、知りたい人が多い公的制度から網羅的に学べるため、先にやっておくと実務に活かすことができますし、追加で専門的な勉強をする際も楽になります。
副業でお金の情報発信をしてみたい
特定の職業の話なので関係のない方には申し訳ないのですが、FP資格はお金関係の情報発信の仕事とも相性が良いと感じます。
例えば、請け負いのフリーライターならFPは特に次の3つの点で優れています。
・高単価案件が比較的多い金融・不動産・相続業界の仕事を受けやすくなる
・登録料なしで生涯FPを名乗れる(CFP、AFPのように登録料・年会費がかかるものもあるので注意)
・1級でも300~500時間ほどで取得できる(勉強経験のある分野があれば短縮可)
クラウドソーシングのライティングの仕事ではFPを必須条件・優遇条件にしている案件もあるため、副業のチャンスはかなり広がると思います。
最近はWeb記事の信頼性を高めるため記事に専門家の監修をつけることがありますが、FPも監修者としてスカウトを受けることがあるので、ライティング以外の仕事の幅も広がります。
副業でライターを始めてみたいけれど、どんな分野で書きたいかわからない場合や、得意分野の募集案件が少なくて困っている場合は、FPで専門領域を拡大し、ブランディングしていくことがおすすめです。
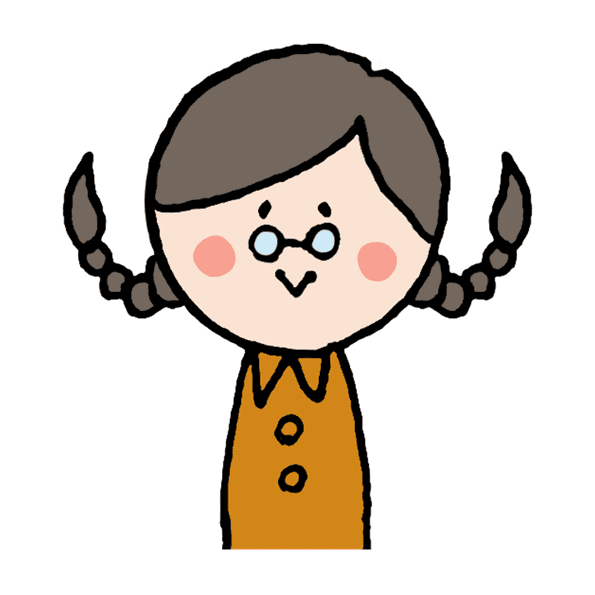
顔出し・本名での記名OKの有資格ライターは特に重宝されますよ!
他にも、YouTubeやブログなど、自分のメディアでお金に関する情報発信をしてみたい方にとって、知名度の高いFPはおすすめです。
FP資格でなくてもいいケースがある
FP試験は出題範囲が広い分、一つ一つの専門知識はそれぞれの専門家に比べるとどうしても浅くなります。1級を取得してもそれは同じです。
また、FP試験は苦手な分野を得意分野でカバーすることもできるため、苦手なところは苦手なままでも何とかなってしまうところがあり、合否結果だけで実力を過信しすぎないほうがよい試験でもあります。
CFP試験のように分野ごとの専門試験もありますが、こちらは合格してもブランディングとして使用する場合は年会費が発生するため、すべての人に向いている試験とはいえません。
もし特定の分野を強化したい場合は、多少時間はかかってもより専門的に学べる資格を先に取得したほうが良いでしょう。
インターネットで調べたり資格系の専門学校のパンフレットなどを見たりして、他の資格も検討してから受験を決めることをおすすめします。
【例】不動産の知識を身に着けたい → FPよりも宅地建物取引士が◎
まとめ
ここまで読んでくださりありがとうございます。
FP試験は、お仕事や学業、家事や育児と併行されて勉強されている方が多いと思います。
お忙しい中、本業も頑張りながら勉強されている方を筆者は心から尊敬し応援しています。
お体には十分お気をつけください。合格をお祈りしております。