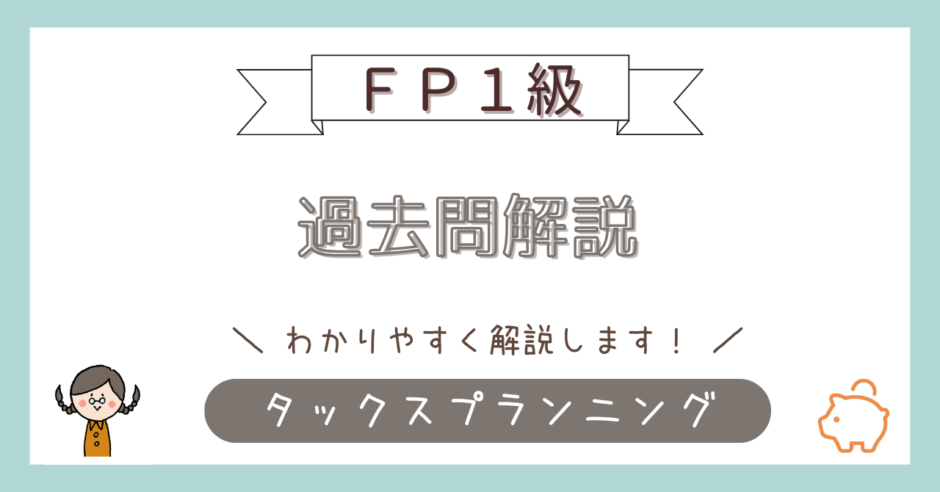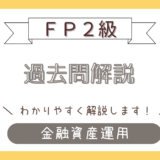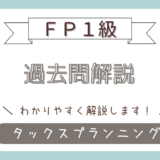一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験2025年9月
【問25】所得税・事業所得
答えをタップしてみよう!
居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人事業主が、販売用の棚卸資産を自家消費したときは、事業所得の金額の計算上、原則として、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。
1:不適切(正答)
個人事業主が販売用の棚卸資産(商品)を私的に消費した際の、事業所得の総収入金額の計算に関する問題です。

八百屋さんがお店の野菜を家族で食べるようなケースになります。
設問では、「原則として、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する」としていますが、原則は「販売価額(×100%)」であり、特例によって「仕入れ価額か販売価額×70%のいずれか大きい額」を総収入金額としてもよいこととされています。
販売用の棚卸資産(商品)を自家消費(家事消費)した場合、原則はその「販売価額」を事業所得の総収入金額に算入します。
しかし国税庁の通達により、仕入れ価額以上で収入として記帳している場合にはその額が「販売価額×70%以上」なら、仕入れ価額でも良いと定められています。もし「仕入れ価額(取得価額)」が「販売価額×70%」を下回るのなら「販売価額×70%以上」を総収入金額に算入します。
つまり「仕入れ価額(取得価額)」か「販売価額×70%」のどちらか大きい額でも良いことになります。
| 特例 | 総収入金額に算入する額 |
|---|---|
| 仕入れ価額>販売価額×70% | 仕入れ価額 |
| 仕入れ価額<販売価額×70% | 販売価額×70%以上 |

実務では原則を気にする必要はありませんので、選択肢の50%を70%に変えた感じで認識していても支障はないと思います。
ちなみに50%という数字は、消費税の課税売上げの特例で登場する数字になります。課税事業者である個人事業主が棚卸資産を自家消費した場合、原則は棚卸資産の時価を課税売上げに計上して申告することになります。しかし、ここでも通達による特例で、仕入れ価額か販売価額のおおむね50%相当額以上の金額で申告したなら、その額でもよいこととなっています。
【個人事業主の自家消費】
・所得税…販売価額×70%
・消費税…販売価額×50%
2.個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2:正しい(◯)
選択肢のとおりです。事業の遂行に付随して生じた次のような収入は事業所得の総収入金額に算入されます。
・事業の遂行上取引先又は使用人に対して貸し付けた貸付金の利子
・事業用資産の購入に伴って景品として受ける金品
・新聞販売店における折込広告収入
・浴場業、飲食業等における広告の掲示による収入
・医師又は歯科医師が、休日、祭日又は夜間に診療等を行うことにより地方公共団体等から支払を受ける委嘱料等
・事業用固定資産に係る固定資産税を納期前に納付することにより交付を受ける報奨金
したがって利子所得ではなく、事業所得になります。
3.個人事業主が、生計を一にする配偶者が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、その配偶者に支払う家賃は必要経費に算入することができないが、その配偶者が納付した当該建物に係る固定資産税に相当する金額は必要経費に算入することができる。
3:正しい(✕)
事業所得の必要経費の計算において、配偶者や親族に支払った賃料等をどのように扱うかという問題です。
選択肢のとおり、個人事業主が同一生計の配偶者に事業用の建物の賃料を払っても、その賃料は必要経費になりません。しかし、配偶者が支払ったその建物の固定資産税は経費になります。

これだけでは意味不明ですが、何のためのルールかを知れば一気にわかりやすくなります。
個人事業主から同一生計の親族に経費を払っても、同じ一つの財布の中でお金が回っているという考え方になり経費になりません。

それを認めると「同一生計親族に経費を払えば家計にノーダメで税金を減らせる」ことに…
こんなことを国が見逃すはずはありません!
そのため、同一生計の親族に支払う経費は必要経費に算入できないのです。
ただし、その同一生計の家族がその対価の原因となるもの(建物の賃料なら、その建物)で負担している経費があれば、それは必要経費になります。たとえば、同一生計の家族が所有する事業用の建物などの固定資産税です。

個人事業主と同一生計の親族の財布が一つなら、同一生計の親族が事業のために外部に支払ったものは、個人事業主の財布から支払っているのと同じと考えます
このことを知っていれば、選択肢が読みやすくなると思います。
選択肢は「建物の賃料」ですが、同一生計の親族に支払う「給与」については、青色事業専従者給与に該当すれば必要経費になります。
4.個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供した減価償却資産の使用可能期間が1年未満である場合、事業所得の金額の計算上、原則として、その取得価額の全額をその事業の用に供した年分の必要経費に算入する。
4:正しい(✕)
選択肢のとおりです。
使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産は、「少額減価償却資産」として減価償却の対象にならず、全額を使用開始年の必要経費にします。
実務では「10万円未満」の方の印象が強いですが、「1年未満か10万円未満」の「どちらか一方」に該当すれば、このルールが適用されます。
なお、令和4年4月から「貸付け(主要な事業として行われる貸付けを除く)」に使用されるものが少額減価償却資産から除外されています。
そのため、選択肢に「原則として」が入っているのだと思います。

この改正は、ドローン等のレンタルを使った課税の繰り延べスキームが問題になって改正されたと言われています。
累進課税による税負担を下げるため、レンタル需要のある少額な資産を大量に買って経費を増やして節税し、翌年以降にその購入費をレンタル収入で回収することで、所得を平準化させるようなイメージです。