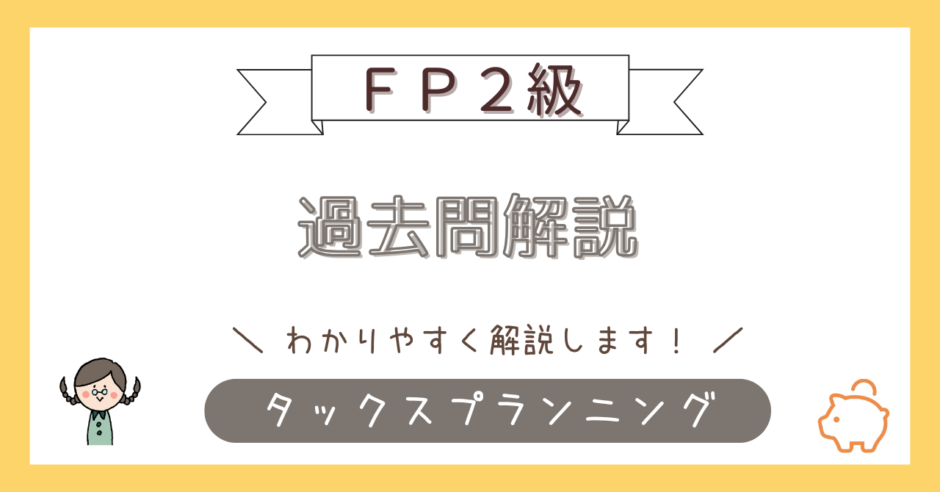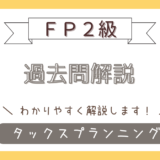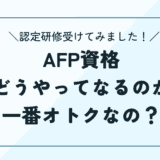FP1級の筆者が、2024年9月のFP2級の学科試験のタックスプランニングを勝手に解説します。
日本FP協会2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2024年9月
【問36】法人税
正答をタップしてみよう!
法人税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.法人税の納税地は、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
1:誤り(✖)
内国法人の法人税の納税地は、法人の本店または主たる事務所の所在地であり、代表者個人の住所ではありません。したがって選択肢は誤りです。
(内国法人の納税地)
第16条 内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。
外国法人の場合は、判定方法が異なります。
2.法人は、法人税の納税地に異動があった場合、異動届出書を異動前および異動後の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2:誤り(✖)
平成29年度税制改正における、手続きの簡素化の一環で行われた改正になります。
改正前は、異動前と異動後の両方の納税地の税務署長に提出しなければなりませんでしたが、改正後は、異動前の納税地の税務署長にのみ提出すればよいこととなりました。
(納税地の異動の届出)
第20条 法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合(中略)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
3.新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
3:誤り(✖)
設立事業年度から法人税の申告を青色申告で行うには、①設立の日から3か月経過した日、または②その事業年度終了日とのいずれか早い日の前日までです。
4.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
4:正しい(正答)
問題文のとおりです。
期末資本金等の額が1億円以下であり、大法人に支配されているなど一定の要件に該当しない中小法人については、通常なら23.2%である法人税率が、その事業年度の所得金額のうち800万円以下の部分について15%となります。
【問37】法人税
正答をタップしてみよう!
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。
1:誤り(✖)
減価償却費として損金に算入できる額には償却限度額として上限が決められています。
超過分がある事業年度は、それを「償却超過額」として所得に加算し、法人税申告を行わなければなりません。
2.法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。
2:誤り(✖)
法人が支出した寄附金は、寄附の相手によって損金に算入できる額が異なります。
特定公益増進法人に支出した寄附金には損金算入限度額があるため、全額を損金の額に算入することができるとする、本選択肢は誤りです。
全額を損金の額に算入することができるのは、国または地方公共団体への寄附金です。
3.法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。
3:正しい(正答)
適切です。交際費には損金不算入となる部分がありますが、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」は、そもそも交際費に当たらない費用として取り扱うことが定められています。(租税特別措置法第61条の4第1項)
このことから、上記の飲食費を支出した場合は、「交際費」ではなく「会議費」などとし、選択肢のように全額損金に算入します。
4.法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
4:誤り(✖)
法人が納付する税金は、法人税の損金に算入できるものとできないものがあります。
【損金に算入される税金】
・法人事業税、事業所税
・不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税
・国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金
【損金に算入されない税金】
・法人税、地方法人税、法人住民税(都道府県民税および市町村民税)の本税
・各種加算税、各種加算金、延滞税、延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)、過怠税
したがって、法人税の本税および法人住民税の本税を「損金に算入できる」とする、この選択肢は誤りです。
【問38】消費税
正答をタップしてみよう!
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人事業者における特定期間とは、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいう。
1:正しい(✖)
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者や、特定期間における課税売上高または給与支給額が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
通常、基準期間は前々事業年度であり、特定期間は前事業年度の開始6ヶ月間です。
個人事業主の事業年度は、1月1日から12月31日であるため、その特定期間は、通常、その前年の1月1日から6月30日になります。
したがって、選択肢は正しいです。
2.簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
2:正しい(✖)
簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者に限り選択できる制度になります。
したがって、選択肢は正しいです。
本来、消費税の申告納税額は、売上税額から仕入税額を控除した差額となります。
一方、売上規模がそれほど大きくない事業者にまで厳格な仕入税額の管理を求めるのは大変なので、簡易課税として、売上税額に一定の仕入率を乗じた額を仕入税額とみなして申告することが認められています。
3.簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3:正しい(✖)
簡易課税制度を選択する場合、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日、つまり、適用を受けたい事業年度が始まる前に、税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
一度適用されると、それ以降の事業年度は継続して適用されます。
4.消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4:誤り(正答)
消費税の確定申告書の提出期限は、原則として、各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内です。法人税と同じになります。
(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)
第45条 事業者(中略)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。(以下省略)
法人税には、定款の定め等により申告期限の延長を受けられる特例がありますが、消費税にも同じ特例があります。
【問39】会社と役員の取引
正答をタップしてみよう!
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
1:誤り(正答)
法人から役員個人に、適正な時価よりも低い金額で資産が譲渡された場合、その時価と譲渡価額の差額相当額は、法人から役員個人への経済的な利益の供与とみなされます。
問題は、この時の個人の課税関係です。
まず、法人から個人への利益の供与は所得税の対象になります。贈与税ではありません。(下記参照)
次に、どの所得に分類されるかになりますが、譲渡を受ける個人がその法人の役員や従業員であれば、その差額相当額は給与所得(現物給与)の収入金額に算入します。
選択肢は、これが「雑所得」となっていますので誤りです。
もし「個人から個人」に対し、時価よりも著しく低い対価で資産を譲渡した場合、時価と対価の差額相当額は贈与とみなされて贈与税の課税対象になりますが、今回は「法人から個人」であるため、贈与税の課税対象になりません。
2.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
2:正しい(✖)
選択肢のとおりです。ちなみに「賃貸料相当額」には計算式があり、それを使って計算すると相場の家賃よりもかなり安くなることが多いです。
3.会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
3:正しい(✖)
どちらが利益を受けたのか、文章から読み取れるかどうかがカギとなる問題です。選択肢は、「個人→法人」に時価より低い価額で資産を売却しています。この場合、利益を受けたのは法人であり、資産の時価と法人に支払われた対価との差額が、法人の受贈益として、益金に算入されます。簿記の知識があれば、仕訳の形でイメージするとわかりやすいかもしれません。
【会社の仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 時価◯◯円 | 現金預金 | 対価◯◯円 |
| ‐ | ‐ | 土地受贈益 | 差額 |
4.会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
4:正しい(✖)
前の選択肢と同じで、どちらが利益を受けたのかを文章から読み取れるかどうかがカギとなる問題です。この選択肢は、役員個人から会社が、借りたお金の返済を免除してもらっています。つまり、利益を受けたのは会社です。ここからは選択肢3と同じで、債務を免除された金額(役員からの借入金の額)が、法人の受贈益として益金に算入されます。
【会社の仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 役員借入金 | ◯◯円 | 債務免除益 | ◯◯円(借入金と同額) |
【問40】適格請求書等保存方式(インボイス制度)
正答をタップしてみよう!
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けると、消費税の課税事業者となる。
1:正しい(✖)
選択肢のとおりです。適格請求書を発行できるのは消費税の課税事業者に限られます。したがって、免税事業者から課税仕入れを行っても、買い手企業は仕入税額控除を計上できません。
経過措置により、令和11年9月30日までは仕入税額相当額の一定割合まで控除が認められます。
2.適格請求書発行事業者の登録に係る効力は、事業者が登録の通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日から生じる。
2:正しい(✖)
選択肢のとおりです。インボイス登録の効力は、登録申請者への通知日にかかわらず、登録簿に登載された日から生じます。「登録簿に登載された日」がわかりづらいですが、これは「登録日」のことです。「後から郵送する登録通知書の作成日とかではなくて、「登録日」からインボイス登録の効果は生じますよ」という内容になります。(消基1-7-3)
登録手続きの混み具合を予想し、通知書の交付が遅れても、登録申請者が希望する日から適格請求書を発行できるようにしたルールと考えられます。
3.適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付するためには、消費税の簡易課税制度の適用を受ける必要がある。
3:誤り(正答)
消費税の簡易課税制度と適格簡易請求書は別の制度であり、関連性はありません。
「適格簡易請求書」とは、一定の業種(例:小売業、飲食店業、タクシーなど)に認められた、簡易な要件で交付できるインボイスのことです。イメージはスーパーのレシートであり、交付する相手(お客さん)の氏名や名称など一部の事項の記載を省略することが認められています。
「適格簡易請求書」は不特定多数を相手にする業種の性質上、認めざるを得ない対応ですので、その適用に簡易課税制度を選択しているかどうかは関係ありません。
「消費税の簡易課税制度」とは、消費税の課税方式の一つです。業種ごとに定められたみなし仕入率を使って仕入税額控除を計算できるため、原則の方式よりも少ない知識と手間で消費税の経理ができます。また、原則の方式より納税額を少なくできることが多いです。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者において選択することができます。
ちなみに簡易課税事業者は、仕入れ先がインボイス登録をしていようといまいと納税額は変わりません。免税事業者と取引をしても特に損をしない業者の一つです。
4.適格請求書には、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号や税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要とされる。
4:正しい(✖)
選択肢のとおりです。
【適格請求書の記載事項】
・発行者の氏名または名称
・発行者のインボイス登録番号
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに区分した対価の合計と適用税率
・税率ごとに区分した消費税額
・交付相手の氏名または名称
【(参考)適格簡易請求書の場合】
・発行者の氏名または名称
・発行者のインボイス登録番号
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに区分した対価の合計(ここまでは同じ)
・税率ごとに区分した消費税額または適用税率(どちらかで良い)
(交付相手の氏名等は不要)