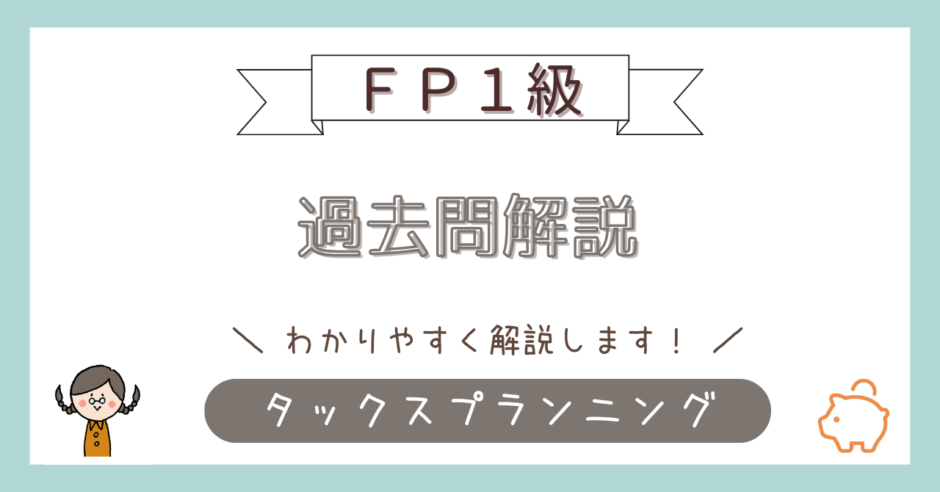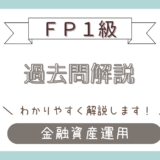一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験2025年9月
【問28】所得税・所得控除
答えをタップしてみよう!
所得税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1.居住者が、年の途中で国内に住所等を有しないこととなるために納税管理人の届出をした場合、納税管理人は、原則として、当該納税者の所得について、国内に住所等を有しないことになった日から4カ月以内に確定申告をしなければならない。
不適切(正答)
出国までに納税管理人を指定した場合、非居住者になった年の確定申告は、通常どおりその年の翌年2月16日から3月15日までに行います。
選択肢はこれにあたると考えられるため、誤りです。

選択肢は納税管理人を選択せずに非居住者となる場合との引っ掛けです
納税管理人を指定せずに出国する場合、その年の「1月1日から出国日」の所得の確定申告を出国の時までに行わなければなりません。この「出国の時までに行う確定申告」のことを準確定申告といいます。
準確定申告には、納税者が亡くなった時と納税者が出国して非居住者になる時の2パターンがあり、選択肢のように「4か月以内」が期限となるのは、納税者が亡くなった場合です。
亡くなった人の準確定申告の期限:相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
2.確定申告により納付すべき所得税額の2分の1に相当する金額以上の所得税を納期限までに納付した者が、納期限までに納税地の所轄税務署長に延納届出書を提出した場合、原則として、その納付した年の5月31日までその残額の納付を延期することができる。
正しい(✖)
選択肢のとおりです。

「延納」とは、所得税・贈与税・相続税における制度であり、所得税と他の2つの税では制度が異なります。今回は、所得税の延納制度からの出題です。
納税の「猶予」とは別の制度です。これは法人税や消費税にも適用されます。
所得税の確定申告による納税額の納期限は、通常3月15日(振替納税の利用者は振替日)までです。
この期限までに全額を納税できない時の対応の一つに「延納」の制度があります。
延納を利用すると、納税額の2分の1以上を通常の納期限まで、残りを5月末までに納税することになります。
納税額の半分相当を、約2か月待ってもらえるイメージです。
延納届出書は、確定申告書第一表の右下にあり、確定申告の際に記入して提出します。記入欄には、「申告期限までに納付する税額」(2分の1以上の金額)と「延納する額」(5月末までの納税する残額)を記載します。

延納している間(3月16日から5月31日まで)は年0.9%の利子税がかかるため、税務署から納付書が送られてきます。

利息みたいな税がかかるのね…
ちなみに振替納税(銀行引き落とし)の納期限は「振替日」で、だいたい「4月中旬~下旬ころ」となります。つまり振替納税を利用すれば、利子税なしで通常よりも約1か月、納期限を伸ばせることになります。
3.確定申告書を提出し、納付した所得税額が計算の誤りにより過大であったことが法定申告期限後に判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求書を提出して納めすぎた税金の還付を受けることができる。
正しい(✖)
選択肢のとおりです。
更正の請求とは、すでに行った納税申告に誤りがあり納税額が過大となっていた場合などに行える手続きです。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内であり、この期間内に「更正請求書」を提出する必要があります。
所得税以外にも、申告を必要とする国税に共通する期限となります。
4.年末調整の対象となる給与所得者の給与所得以外の所得が一時所得のみである場合に、一時所得の金額に2分の1を乗じた後の金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。
正しい(✖)
選択肢のとおり、一時所得は2分の1を乗じた「後」の金額で、確定申告の要否を判定します。
筆者は、「年末調整の対象となる給与所得者」の給与所得か、「年末調整の対象となる給与所得者の給与所得」なのか迷いました。「年末調整の対象となる(給与所得者の)給与所得」と読むのが正解のようです。
間違って前者で読んだ場合、年末調整の対象となる給与所得者(勤務先に扶養控除等申告書を提出した給与所得者)に年末調整をされなかった給与(アルバイトなど)がある場合、その額により確定申告が必要になるケースがあるため引っ掛けかと思いました(本業(甲欄)+アルバイト収入(乙欄)のような人です)。