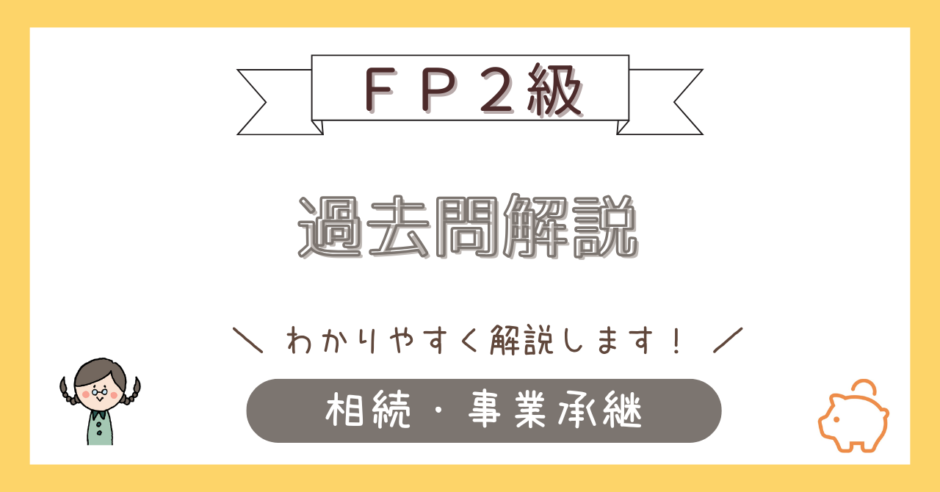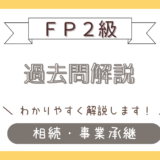FP1級の筆者が、2024年9月のFP2級の学科試験の相続・事業承継を、自分の勉強のために勝手に解説します。
日本 FP協会2級ァイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2024年9月
【問51】民法上の贈与契約
正答をタップしてみよう!
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
1:正しい(正答)
定期贈与とは、一定時期ごとに財産を無償で与える契約をいいます。(例:「毎年10万円を贈与する」)
定期贈与の効力は、当事者のいずれか一方が亡くなると失われます。民法の条文どおりの選択肢です。
2.負担付贈与は、受贈者の負担により利益を受ける者が贈与者以外である場合には成立しない。
2:誤り(✖)
負担付贈与とは、贈与契約の一部として、受贈者に一定の義務を負担させる契約をいいます。
例:「私が死んだら自宅をあげるから、その代わりに飼い猫の世話をして」
選択肢では、負担するのが受贈者である部分は合っていますが、それにより利益を受ける者の範囲が誤りです。利益を受ける者については特に制限されておらず、贈与者でも、第三者でも、不特定多数でも構いません。
3.死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者のみの意思表示により成立する。
3:誤り(✖)
死因贈与とは、贈与者が亡くなったときに効力が生じる贈与契約のことです。
贈与者が亡くなることで効力が発生する点において、死因贈与は遺贈(遺言書による贈与)と似ています。そのため、死因贈与には遺贈の規定が法律で準用されており、問題文の前半は合っています。(民法第554条)
しかし、遺贈は亡くなった人の生前の思いを尊重するという特殊な性質を持つため、遺贈は亡くなった人の一方的な意思表示のみ(生前に作成した遺言書)で成立しますが、死因贈与は生きている人間同士のお互いの意思表示がなければ成立しません。
他にも、遺言は満15歳から親権者の同意なしで行えるなどの違いがあります。(死因贈与は18歳)
4.書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
4:誤り(✖)
書面によらない贈与について、各当事者が解除できることは合っていますが、履行が終わった部分については解除できません。
民法の条文どおりの内容になります。
【問52】贈与税の配偶者控除
正答をタップしてみよう!
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1.過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。
1:正しい(✖)
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で行う、居住用不動産やそれを取得するための金銭の贈与について、2,000万円分まで贈与税を非課税とする制度です。(通称:おしどり贈与)
夫が亡くなった後の妻の生活保障などの意図をもって特別に認められた制度であるため、同じ配偶者からの贈与で使えるのは一度だけになります。
再婚相手との間であれば再び使うことは可能です。つまり、1人の配偶者につき1回となります。ただし、その配偶者との婚姻期間も20年以上なければ使えません。
2.本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。
2:誤り(正答)
婚姻期間が20年であるかどうかは、婚姻の日から贈与の日までの期間で判断します。
当たり前のことのようですが、贈与税には、問題文のように「贈与のあった年の1月1日」を判定基準とする制度がいくつかあるため混同しないよう注意が必要です。
「贈与のあった年の1月1日」で判定するものは基本的には「年齢」なので、参考にしてください。
3.配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない。
3:正しい(✖)
贈与税の配偶者控除と、相続税の生前贈与加算の関係を問う問題です。
相続税には、相続開始前の「一定期間」に被相続人(亡くなった人)から生前贈与された財産がある場合、それを相続税の計算に加算しなければならない「生前贈与加算」のルールがあります。
「一定期間」については、税制改正により、現在、3年から7年に段階的に移行中です。
しかし、おしどり贈与による控除は、夫が亡くなった後の妻の生活保障などを目的としているため、せっかく非課税で受け取った住宅に、結局のところ相続税がかかるのでは片手落ちです。
そのため、配偶者控除を活用して非課税とした分については、生前贈与加算の対象期間内に行われた贈与であったとしても、加算しません。
住宅取得資金、結婚・子育て資金、教育資金の3つの非課税特例も、同じ扱いになります。
4.居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる。
4:正しい(✖)
居住用不動産の定義を問う問題です。
税法では「専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋」と定義されており、住宅と土地をセットで贈与することは条件としていません。
国税庁の通達でも、家屋の敷地である土地のみの取得が本制度の対象になると明記されています。
例えば、夫名義の家屋と土地に夫婦で暮らしている場合、土地のみを妻に贈与するのも可ですし、土地の持ち分を一部妻に贈与するのも可となります。
相続税法基本通達21の6-1
(前略)次に掲げる土地若しくは土地の上に存する権利(中略)又は家屋は、同項に規定する居住用不動産(中略)に該当するものとして取り扱うものとする。
(1)省略
(2)受贈配偶者がその者の専ら居住の用に供する家屋の存する土地等のみを取得した場合で、当該家屋の所有者が当該受贈配偶者の配偶者又は当該受贈配偶者と同居するその者の親族であるときにおける当該土地等(以下略)
(3)省略
家屋のみの贈与でも対象になります。
【問53】相続時精算課税制度
正答をタップしてみよう!
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1.父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、その選択をした年分以後、所定の手続きにより、その父から受ける財産の贈与について暦年課税に変更することができる。
1:誤り(✖)
できません。「暦年贈与→相続時精算課税」は一方通行です。
2.父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、同一年中に母から受けた財産の贈与についても本制度が適用され、母からの贈与について暦年課税により贈与税額を計算することはできない。
2:誤り(✖)
相続時精算課税を選択した場合の効果範囲を問う問題です。
相続時精算課税の選択は、贈与者ごとに行います。
具体的には、贈与を受けた者が税務署に対し、「◯◯(父など特定の人物)からの贈与は、以後、相続時精算課税を使います」という趣旨の「相続時精算課税選択届出書」を提出することで、この「◯◯(父など特定の人物)」にのみ相続時精算課税が適用されます。
つまり、贈与を受けた人物(子など)の判断で、父からの贈与はこの書類を提出して相続時精算課税を適用し、母からの贈与はこの書類を提出せず引き続き暦年課税を適用することができます。
3.父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、贈与者の年齢に係る要件はあるが、受贈者の年齢に係る要件はない。
3:誤り(✖)
相続時精算課税を適用できる年齢の組み合わせは、受贈者(子や孫など)は18歳以上、贈与者(親や祖父母など)は60歳以上の場合に限られます。年齢の判定日は「贈与のあった年の1月1日」です。
例外的に、住宅取得等資金の非課税特例と併用する場合、贈与者が60歳未満でも相続時精算課税は選択できます。「他の制度の適用状況は考慮しない」的な一文がなく偶然にもここまで正解の選択肢がないため、「ひっかけ」を疑った方もいるでしょう。
4.父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、その適用の対象となる贈与財産の種類や贈与回数について制限はない。
4:正しい(正答)
相続時精算課税に財産の種類の制限や回数制限は特にありません。
非課税となる2,500万円を超えると超過分に一律20%の贈与税が発生するようになりますが、贈与自体は何回でも実行することができます。
【問54】任意後見制度
正答をタップしてみよう!
任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.任意後見制度では、本人が十分な判断能力を有しているときに、本人が、任意後見人となる者や委任する事務を契約によりあらかじめ定めておくことができる。
1:正しい(✖)
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。
法定後見制度の場合、家庭裁判所によって選任された人が成年後見人になりますが、任意後見制度の場合、自分で選んだ人を後見人にできるメリットがあります。
任意後見制度とは、民法の法定後見制度とは異なり、お互いの合意による契約になります。ただし、内容が特殊であるため、その効果や手続きは「任意後見契約に関する法律」という個別の法律にきちんと定められています。
2.任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。
2:正しい(✖)
任意後見契約の、通常の契約とは異なる部分の知識を問う選択肢です。
選択肢のとおり、任意後見契約の締結は、公正証書を作成して行わなければなりません。
任意後見契約は、判断能力が低下した後の自身のさまざまな権利を他者に委ねる、とても重要な契約です。なるべくトラブルがないよう、手続きは厳格に定められています。
3.任意後見契約は、本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況となった時からその効力が生じる。
3:誤り(正答)
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見人を監督する任意後見監督人が選任された時から効力を生じます。(任意後見契約に関する法律第2条第1号)
本人の判断能力が低下しただけでは契約の効力は自然発生せず、任意後見監督人が家庭裁判所により選任されて初めて効力が発生するのです。
任意後見監督人とは、任意後見人(任意後見契約の相手)が、適正に仕事をしているかを監督する者です。
家庭裁判所への申し立ては、本人の判断能力が低下した時に、本人、配偶者、親族、任意後見人(任意後見契約の相手。厳密にはまだ「任意後見受任者」)が請求できます。
4.任意後見監督人は家庭裁判所により選任されるが、任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は任意後見監督人となることができない。
4:正しい(✖)
任意後見監督人は、任意後見人の仕事を監督する役割です。公正な判断が求められるため、任意後見人となる本人や、その配偶者、直系血族、兄弟姉妹といった関係者は就任することができません。
【問55】遺産分割
正答をタップしてみよう!
遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
1:正しい(✖)
被相続人(亡くなった方)は、生前に作成した遺言書により、遺産分割の方法を定めることや遺産分割を禁止することが認められています。
ただし、遺産分割の禁止期間は5年を超えることはできません。民法の条文のままの問題です。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2.共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。
2:正しい(✖)
平成30年の民法改正により、それまで明文規定がなかった、共同相続人による一部分割を認める条文が新たに設けられました。共同相続人とは、相続人が2人以上いる相続での相続人の呼び方です。
遺産分割の争いは長期間に及ぶこともあり、その間、すべての遺産が拘束されると何かと不都合が生じます。そこで、争いのない一部の財産だけ先行して分割できるよう明文化されました。
(遺産の分割の協議又は審判)
第907条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
3.遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる。
3:正しい(✖)
共同相続人の間で、遺産分割協議をしても調わない場合や協議ができない場合は、それぞれの相続人が、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判の申立てをすることができます。
民法第907条第2項の条文から出題されています。
(遺産の分割の協議又は審判)
第907条
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
4.遺産分割協議書は、公正証書によって作成しなければならない。
4:誤り(正答)
遺産分割協議書は、主に遺産分割に基づく財産の名義変更などの手続きを行う際に使用されますが、必ずしも公正証書である必要はありません。
公正証書にする必要はありませんが、全員の署名または記名押印(実印による押印)と、実印にかかる印鑑証明書が必要になります。
なお、公正証書にすることには、書き方の不備を防止できるほか、公文書扱いになることにより限られた場面にはなりますが一部の手続きが執行しやすくなるなどの利点もあります。