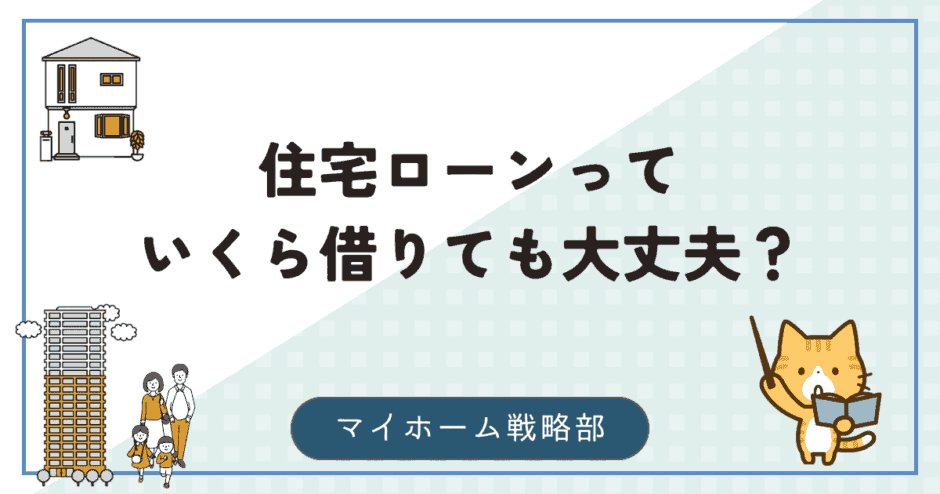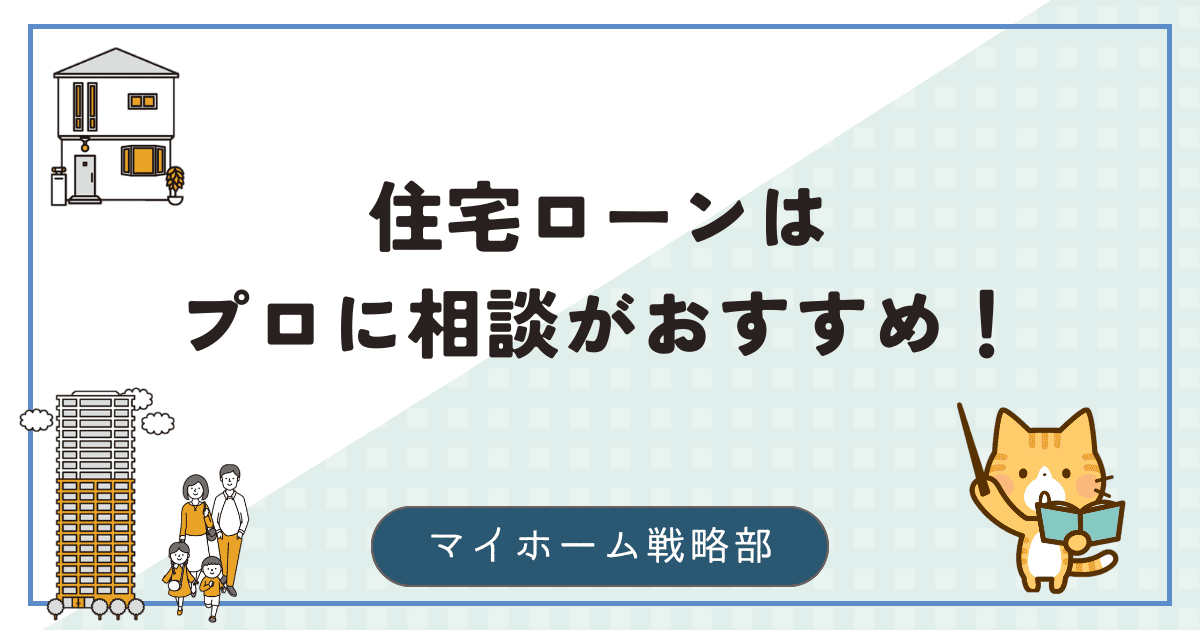住宅ローンをどのくらい借りられるのかを知ることによって、どの価格帯の住宅を選択肢に入れられるかが変わります。
住宅ローンの借入可能額はいくつかの要素によって決まりますが、もっとも大きな決定要素は、住宅ローンを借り入れる「本人の年収」です。
住宅ローンの借入可能額と年収の目安
住宅ローンの借入可能額は、年収の5〜8倍になると言われています。
例えば、住宅ローンの一つである「フラット35」において、返済期間30年でシミュレーションすると、おおむね年収の8倍程度の借入可能額が提示されます。
例:年収500万円、金利年1.9%、返済期間30年
→借入可能額の概算:約4,000万円となります。
(※)金利については新機構団信付きの【フラット35】を参照しています。
(参考)住宅金融支援機構【フラット35】:クイックシミュレーション

個人的には、公務員でも5倍くらいになる人が多い印象です
8倍も借りられる人は少ないと思っています
ただし、年収だけでは決まりません。住宅ローンの借入可能額を左右する他の要素も見ていきましょう。
住宅ローンの借入可能額が決まる仕組み
住宅ローンの借入可能額は、ローンを申し込んだ金融機関における「審査」によって決まります。
「審査」の基準は金融機関によって多少変わるかもしれませんが、大まかには以下のような基準を柱に行われています。
- 収入
- 返済負担率
- 他の借入状況
- 本人の信用力
- 担保価値
一つずつ見ていきましょう。
収入(年収)
ローンを申し込む人の年収です。前述のとおり年収の5倍~8倍が目安になります。
返済負担率
「返済負担率」とは、年収に占める年間返済額の割合のことで、「返済比率」とも言います。
平均的な年収以上の方であれば、この「返済負担率」は年収のおおむね25〜35%以内になります。

年収の倍率との違いは、1年あたりの返済額が審査の対象になっているところです
こちらをご覧ください。
【例1】
・年収500万円、金利年1.9%、返済期間30年
→ 借入可能額の概算:約4,000万円
【例2】
・年収500万円、金利年1.9%、返済期間25年
→ 借入可能額の概算:約3,500万円
先ほど、フラット35のシミュレーターで、年収が500万円の場合、その8倍にあたる約4,000万円の借入可能額が試算されました。
しかし、返済期間を5年短く(30年→25年)すると、借入可能額は約3,500万円に下がります。
返済期間が短いと、1年あたりの返済額が増えるため「返済負担率」が高まるからです。
他の借入状況
住宅以外にも借金がある場合、それらの月々の返済額や残額も、住宅ローンの審査では考慮されます。
さまざまなローンの返済が重なると、生活が破たんして返済が滞ってしまうからです。
住宅ローンの場合、クレジットカードのローンなどに適用される「総量規制」(年収の3分の1を超える貸付けを禁止する制度のこと)の適用はありませんが、こうした審査基準があることによって、借金が増えすぎないようになっています。
本人の信用力
住宅ローンの審査においては、本人の信用力もチェックされます。
例えば、過去の決済トラブルなどの信用情報、資産の状況、勤め先の安定性など、返済に関わる事項をチェックをし、その結果が、住宅ローンの借入可能額や、場合によっては金利に反映されます。
担保価値
住宅ローンは、購入した住宅を担保に金銭を借りる仕組みになります。
住宅ローンの契約者が万が一にも返済不能となった場合、金融機関はその住宅を差し押さえることで残りのローンを回収します。
審査でも、当然ながら、返済不能になった場合の回収可能性(押収した不動産で借金を精算できる可能性)を秤にかけて借入可能額を決めています。
そのため、担保となる住宅の不動産としての価値も、借入可能額に大きな影響を与えます。
住宅ローン、もしかして「借りすぎ」?
なぜ返済不能が起こるのか
いわゆる「住宅ローン破綻」は毎年一定数発生しています。
それには、以下のようなことが原因になると考えられます。
・収入が減った(失業や病気など)
・住宅ローン控除期間が終わって手取りが減った
・子どもの教育などで大金が必要になった
・金利が上昇し、返済総額が増えた(変動金利の場合のみ)
・住宅を買った後の維持管理のコストが、予想以上に高かった
どれか一つによって住宅ローン破綻は起こるものではなく、こうした要素が複合的に発生して、返済ができなくなるものと考えられます。
事情はそれぞれですが、ここでは、そもそも銀行から借りる時点でちょっと「借りすぎ」だったのではないかという話をします。
そもそも「借りすぎ」の可能性がある

そもそも銀行が「貸して良い」って判断してくれた金額なのに、どうして返済不能になるんですか?

確かに、銀行がそれだけの額を貸す価値がある人物だと判断したことは間違いありません
住宅ローンは、金融機関がきちんと審査をして金額を決めるため、住宅ローンを借りた人にそれだけの額を貸し付ける価値があったことには間違いありません。
それなのに、どうして返済できなくなるようなことが起こるのでしょうか。

銀行が見ているのは「返済できるかどうか」ではなく、「回収できるかどうか」だからです
銀行は、返済負担率や他の借金の有無などを踏まえて審査するため、基本的にはその人が返済できる額を貸し付けます。
とは言え、住宅ローンの借入可能額は、返済不能になった時の物件の担保価値も視野に入れて決められています。
つまり、最初から破綻した時のシナリオも用意して貸している金額なので、「絶対に返済できる」と責任をもって判断した金額ではありません。
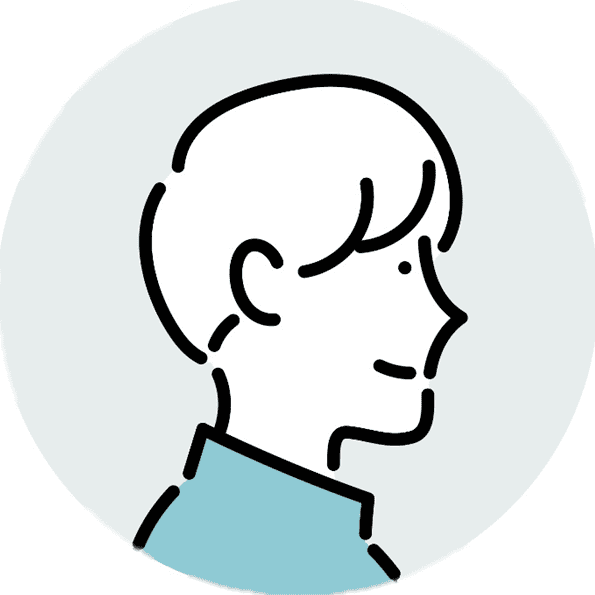
だから、借りた後に事情が変わると返済が苦しくなることがあるのか…

長い返済期間の間、何が起こるかわかりません
限度額いっぱいに借りると、「借りすぎ」になる可能性があります
住宅ローンはいくらに収めるべきか
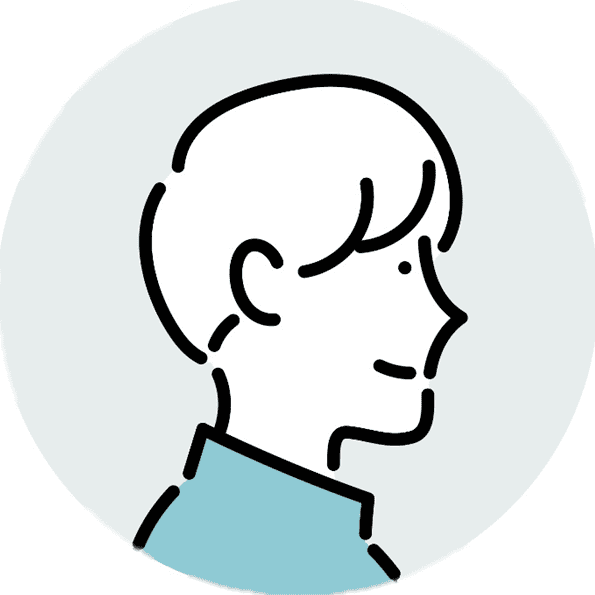
住宅ローンが借りすぎにならないための目安はないのですか?

毎年の返済額が「手取り年収」の20%以内に収まるか、というものが一つの目安になります
返済不能にならないよう、一般的に住宅ローンは、毎年の返済額を「手取り年収」の20~25%以内に収めることが推奨されています。
「手取り年収」とは、年収から税金や社会保険料などの公的な支払いを除いた、実際に生活に使える金額になります。
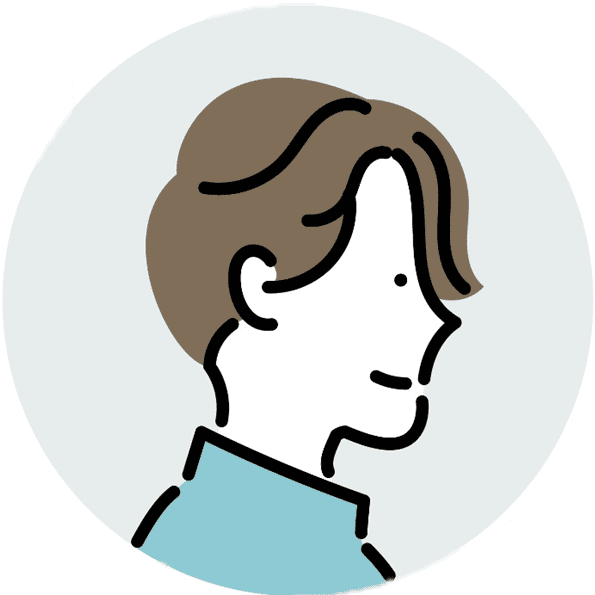
いやいや、収支が黒字なら何%でも関係ないでしょ
住居にお金をかけたい人もいるわけだし

おっしゃるとおりです
ただ、住宅ローンには、わかりやすい目安が必要になる「理由」があるのです
上記の通り、「収支が黒字なら何%だろうと問題ない」というのは、そのとおりです。
それでは、なぜこのような目安が存在するのかというと「借金に慣れていない人が多い」からです。
そもそも、普通の人がこれほど高額で長期となる借金の返済を経験することは、住宅ローン以外にまずありません。初めての借金になる人もいるでしょう。
そのため、多くの人にとって収支のバランスを管理する上で「わかりやすい目安」が必要になります。
そこで、一つの目安として提示されているものが、手取り年収の20%~25%なのです。
いくらまで借りるかは、専門家に相談することもできます
収支のバランスは自分で考えなければならない
手取り年収の20%~25%のルールは一つの目安になりますが、これがすべての人にとって安全なローンの額ではありません。

20%以下でも大変な出費ですから、家計の収支のバランスには常に注意しなければなりません
どのような割合であったとしても、収支がカツカツの状態であれば、家計に関する何らかの変化が重なるとたちまち赤字に転じてしまい、返済が苦しくなっていきます。
例えば、物価の上昇、変動金利の上昇、教育資金の増加(お子さんの進路変更など)、収入の変化などが考えられます。
住宅ローンをいくらまで借り入れるかは、その家庭・その人の収支のバランスと、将来の生活や教育に必要な資金を見極めて決めることが大切です。
まとめ
住宅ローンは、一般的には年収の5〜8倍ほど借りることができます。
しかしそれは、本人が無理なく返済できるかどうかまで配慮されているわけではありません。
住宅ローンはその家庭・その人ごとの収支のバランスを見て決めることが大切です。
無理のない生活を送るためにも、自身の収入や支出をしっかりと見極め、慎重に計画を立てることが重要です。
住宅ローンの返済額や金利は専門家に相談することもできます