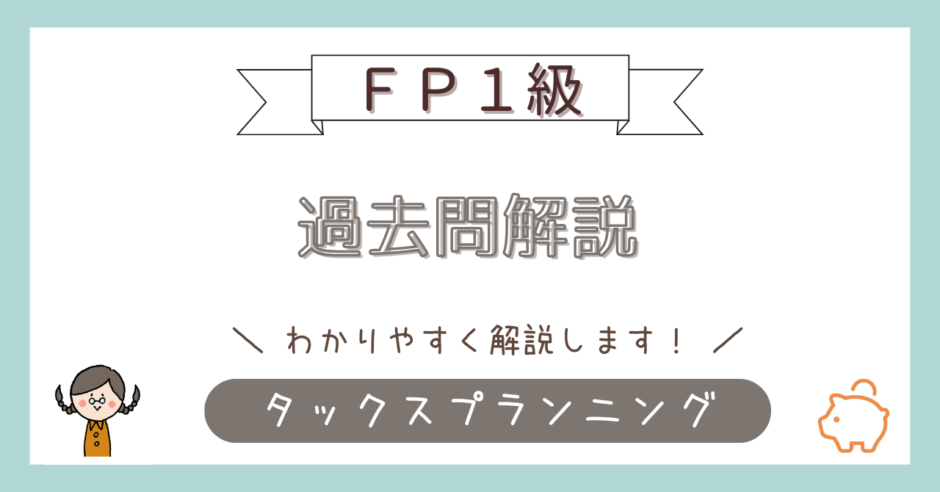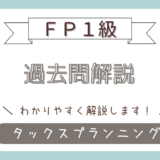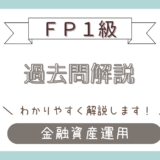一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験2025年9月
【問26】所得税・譲渡所得
答えをタップしてみよう!
居住者に係る所得税の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1.借地権を有する者が当該借地権の設定されている底地を取得し、その後、その土地の全部を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、当該土地の取得日は、底地に相当する部分と借地権に相当する部分とに分けて判定する。
正しい(✖)
土地(借地権を含む)の譲渡所得は、その取得日に応じて長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。長期であれば税率は短期の半分で済むため、取得日の判定はとても重要な論点となります。
選択肢は、借地権を設定した土地について借地権者が後に底地部分も取得した場合、取得日を別個に判定しなければならないのかという問いです。
答えは選択肢のとおりで、国税庁通達に定められています。
なお、借地権が設定された土地の所有者(底地の所有者)が後に借地権を取得した「逆パターン」でも同じで、取得日は別個に判定されます。

借地も底地も、それぞれ単独でも取引されるものなので、分けて判定する方が公平です
2.ハウスメーカーに請け負わせて建築した自宅の建物を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、当該建物の取得日は、当該建物の引渡しを受けた日となり、請負契約を締結した日とすることはできない。
正しい(✖)
選択肢1に続き、取得日に関する問題です。選択肢のとおり、請け負いにより他者に建設したもらった資産の取得日は、引き渡しを受けた日となります。
なお、請け負いではなく自ら建設した場合は、その完成日となります。
3.資産を個人に対して通常の取引価額の2分の1未満の金額で譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡した時の通常の取引価額を総収入金額に算入する。
不適切(正答)
選択肢のように、個人→個人に対して、通常の取引価額の2分の1未満で譲渡した場合は、譲渡価額がそのまま譲渡収入となります。
ちなみに選択肢は「個人→個人」ではなく「個人→法人」であれば◯でした。

結果だけ見ると意味不明ですよね…
どうして相手が個人と法人で変わるのか、理由を解説します!
まず、問題文にはありませんが、個人→個人での2分の1未満での譲渡が行われた場合、譲り受けた個人が前所有者の取得日と取得費を引き継ぎます。(所得税法第60条①)
つまりこれは、相続や贈与と同じ、新しい所有者への課税の繰り延べ(先延ばし)の対象なのです。

かつては人が亡くなった時、故人の財産の譲渡益に所得税、そしてその資産の時価に相続税が一度にかけられていました。しかし、納税者から不満が続出し、譲渡益については課税のタイミングを繰り延べ(先送り)するようになったのです。
次の所有者がその資産を売却する時、引き継いだ取得費から譲渡益を計算するため、前所有者の譲渡益は時を経ていつか清算される仕組みです。
一方、個人から法人への贈与や遺贈、時価の2分の1未満の低額譲渡が行われた時は、通常の取引価額(時価)で個人が譲渡したとみなされます。
それではなぜ「相手が法人」だと、個人はその時点で時価で課税されなければならないのでしょうか。
理由は、法人に個人と同じ扱いを適用すると不合理が生じるからです。

個人→個人での課税の繰り延べは、あくまで個人の譲渡益が次の個人の譲渡益になるだけという、同じ税法内でのルールなのでかろうじて成立しています。しかしこれを計算ルールも税率も違う法人所得として引き継ぐことはさすがに無理があるのです。
そのため、個人から法人への贈与や低額譲渡は、譲渡のタイミングで時価で譲渡益を計算し、その場で清算しておく必要があるのです。
4.所有する賃貸アパートの建物およびその敷地を譲渡するために、当該建物の賃借人に支払う立退料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用として総収入金額から控除する。
正しい(✖)
譲渡所得の計算上、譲渡収入から控除できる「譲渡費用」の範囲に関する問題です。
選択肢のとおり、立ち退き料は譲渡費用に該当します。
ちなみに選択肢は「売る時」の話ですが、立ち退き料は「買う時」に買い手が負担することもあります。その場合は、買い手の「取得費」に含めることができ、将来の売却時に譲渡収入から控除できる取得費の一部となります。