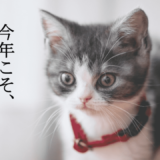ID・パスワード方式を利用すれば、マイナンバーカードやICカードリーダーを持たない人でもe-Taxによる電子申告ができるようになります。
筆者もマイナンバーカードの交付を受けるまでは重宝していました。
しかし、マイナンバーカードの交付を受け、マイナンバーカードで確定申告をするようになって初めてわかったのですが、ID・パスワード方式は中途半端なところも多いサービスです。
この記事では、ID・パスワード方式とマイナンバーカード方式の両方で確定申告を実際にやってみた筆者が、ID・パスワード方式でできないことや、マイナンバーカードによって新しく出来るようになったことを解説します。
約600万人が自分でe-Taxを使って確定申告をする時代に
確定申告書の提出方法には、書面提出のほかに「e-Tax」という国税庁のオンラインシステムを使って送信する方法があります。
国税庁の発表によると、2022年分の所得税の申告件数は約2,295万件であり、このうち592万人については、納税者が自分自身でe-Taxを利用して確定申告をした件数であったとしています。2018年の約5倍に相当する人数です。
スマートフォンからの確定申告も年々便利になっており、ますます確定申告のデジタル化が進んでいくことでしょう。
(参考)国税庁:令和4年分所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
e-Taxで確定申告をすることのメリット
e-Taxによる確定申告には、私たち納税者にとってさまざまなメリットがあります。
e-Taxを利用すれば、自宅にいながら24時間(※)いつでも確定申告をすることができます。
(※)確定申告期は24時間利用可能です
e-Taxで確定申告をすれば、書面で提出するときのように確定申告書を印刷する必要がありません。
また、添付書類(※)についても提出を省略できます。
(※)省略できる添付書類の例:番号通知カードや身分証のコピー、社会保険料や地震・生命保険料の控除証明書など
税務署に行かずに確定申告をする方法には、書類を郵送する方法もあります。しかし、この方法では、確定申告書や添付書類の準備をした上で、郵送の準備が必要になります。
e-Taxで確定申告すれば、この準備も必要ありません。
確定申告書を書面で提出する場合、税務署の収受印(受理印)を押した確定申告書の控えをもらうことができます。
これを郵送でもらうには、確定申告書と一緒に「確定申告書の控え」と「切手を貼った返送用封筒」を同封する必要があります。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxで確定申告書を送信すれば、税務署の受付日時・受付番号が入った確定申告書のPDFデータを即ダウンロードできるようになります。さらに、メッセージボックスには税務署からの受信通知も格納されますので、要らなくなります。
2020年分の確定申告から、青色申告をする個人事業主や不動産オーナーが青色申告特別控除65万円を受けるには、e-Taxによる電子申告をすることなどが追加要件となりました。
e-Taxで確定申告をすることによって、節税できるケースもあるということです。

筆者はこれが目当てでe-Taxを使いはじめました
ID・パスワード方式とは
ID・パスワード方式は、マイナンバーカードなしでe-Taxによる確定申告(電子申告)をするための方法です。2019年1月から導入されています。
マイナンバーカードを必要としない代わりに、税務署での対面確認を経て交付される「IDとパスワード」(利用者識別番号と暗証番号)の入力を、電子証明の代わりとする方法になります。
冒頭にご紹介した国税庁の発表では、例の592万人のうち約7割がマイナンバーカード方式であるとされているため、現在の利用者はそこまで多くないのかも知れません。

税務署で対面確認まで受けたIDとパスワードですから、できれば使い続けたいですよね
筆者もID・パスワード方式を使っていた時期があるのでめちゃくちゃわかります
ID・パスワード方式のままでは出来ないこと
ID・パスワード方式は、個人の確定申告をe-Taxでするためだけの制度です。
下記のような機能を、ID・パスワード方式で使うことはできません。
マイナポータル連携ができない
マイナポータルとは、民間の保険会社・金融機関・証券会社などの情報を、税金や年金などの公的制度と繋ぐサービスのことです。
これを使えば、確定申告書を作成する際に、下記のような控除の情報をマイナポータルからまとめて取得し、個人の確定申告に自動反映させることができます。
・生命保険料・地震保険料の控除証明書
・iDeCoや小規模企業共済の掛け金の控除証明書
・特定口座年間取引報告書
・住宅ローン控除の年末残高証明書
など
このマイナポータルから情報を取得するには、残念ながらマイナンバーカードによる認証が必要になりますので、ID・パスワード方式では使えません。
e-Taxのメッセージボックスがフルで使えない
e-Taxの利用者には、それぞれに「メッセージボックス」が用意されています。
メッセージボックスとは、国税庁や税務署から個人宛てのお知らせが格納されるメールボックスのようなものです。
このお知らせは、マイナンバーカードの認証をしなければほとんど読めません。
筆者のメッセージボックスを使って、ID・パスワード方式でログインして読めるものを確認してみたのですが、下記のようなものだけでした。
・納税方法の登録のお知らせ
・税務署からのお知らせ
など

「ダイレクト納付の登録が完了しました」とか、「インボイス制度の特設サイト見てください」とか、そんな感じです

それ以外のメッセージは鍵マークがついていて見ることができません
ちなみにマイナンバーカードを読み取れば、鍵マークつきの下記のようなメッセージもすべて読むことができるようになります。
・確定申告の受信通知
・各種届出書や申請書の受信通知
・ID・パスワード方式の利用届出
など
上記のとおりID・パスワード方式のお知らせを読むことでさえ、マイナンバーカードの読み取りが必要になります。
メッセージボックス内のメッセージがすべて読めるようになると、いつどんな手続きを行ったのか、さかのぼって確認できることにメリットがあります。
メッセージボックスは格納された日から120日を経過すると「過去分」のボックスに移ります。「過去分」に移されても、特に問題なく閲覧できます。「過去分」は、格納されてから1,900日間(約5年分)を経過するまで保存されます。
他の手続きには使えない
ID・パスワード方式は、「確定申告書等作成コーナー」で作成した書類を送信することしかできません。
「確定申告書等作成コーナー」に対応していない手続きには使えないということです。
・下記①~④の作成
①所得税及び復興特別所得税の確定申告書
②青色申告決算書・収支内訳書
③個人の消費税及び地方消費税の確定申告書
④贈与税の申告書
・上記①~④の更正の請求・修正申告書
マイナンバーカードがあれば、「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカード方式で確定申告ができるようになるだけでなく、「e-Taxソフト」を利用した各種届け出や申請も自宅からできるようになります。
「e-Taxソフト」とは国税庁が無料で提供している、インストール型のソフトです。
あらゆる税務申告・届け出・申請のための書類作成ができる上に、作成した書類は、マイナンバーカードを読み取って電子署名を付与することにより、それらをe-Taxで送信できます。
「e-Taxソフト」は、個人事業主やご自身で会社を経営している人にとって、わりと使いどころのあるソフトになります。
例えば、下記のような手続きも、税務署にわざわざ書面を提出せずに自宅からe-Taxによるデータ送信でできるようになります。
・新しい事業や会社を立ち上げたときの届け出(個人事業の開業届、法人税の法人設立届)
・青色申告をしたいときの申請(青色申告承認申請書)
・従業員を雇って給与を支払い始めるときの届け出(給与支払事務所の開設届)
・引っ越したときや事務所を移転したときの届け出(異動届)
・法人税の申告書・法人消費税の申告書
・インボイス登録をするための申請(適格請求書発行事業者登録申請)
など
これらをメッセージボックスに格納された受信通知をダウンロードして一緒に保管すれば、収受印のある書類(コピー)を返送してもらう必要はありません。
ID・パスワード方式のその他のデメリットや注意点
ID・パスワード方式を使うことには、以下のデメリットや注意点もあります。
利用するために税務署に出向く必要がある
ID・パスワード方式の利用を開始するには、必ず税務署に出向いて対面確認を受けなければなりません。
開庁時間内に出向かなければならないため、対応が難しい人もいるでしょう。
ID・パスワード方式は暫定措置
国税庁は、ID・パスワード方式を「マイナンバーカードが普及するまでの暫定措置」とし、なるべく早めにマイナンバーカードを取得することを推奨しています。
創設された当初は「おおむね3年の暫定措置」(今は単なる「暫定措置」)とされていたこともあり、いつか使えなくなる可能性があります。
IDとパスワードを管理し続けなければならない
ID・パスワード方式では、確定申告書等作成コーナーからe-Taxを使用する度に、税務署から交付された利用者識別番号と暗証番号を使用する必要があります。
ID・パスワード方式を使い続ける間は、この2つをずっと管理しなければなりません。
マイナンバーカードでの手続きをおすすめする理由
ID・パスワード方式よりも使える機能が圧倒的に多い
マイナンバーカードを読み取れば、確定申告書等作成コーナーで確定申告が便利になる上に、確定申告以外の手続きも自宅からできるようになります。
ID・パスワード方式によるデメリットを受けない
マイナンバーカード方式でe-Taxを利用する場合、税務署に出向く必要はありません。
すべて自宅からの手続きでe-Taxを始めることができます。

「暫定措置」とされていることを心配する必要がないことも嬉しいですね
スマホをカードリーダーにできる
スマホをマイナンバーカードのカードリーダーとして使えば、マイナンバーカードを取得するだけでマイナンバーカード方式や、マイナンバーカード認証によって解放される各種手続きを利用できるようなります。
現在、Android・iPhoneの両方でマイナンバーカードの読み取りが可能となっています。
パソコンで確定申告をする人、スマホで確定申告をする人の両方にとって使えます。
おすすめのICカードリーダー
スマホでマイナンバーカードを読み取ることがうまくいかなかったり、何となくスマホにマイナンバーカードを読み取らせることが不安だという人もいらっしゃるかもしれません。
読み取りに使うアプリはデジタル庁がリリースしていますので、そこまで心配する必要はないと思いますが、気になる人はICカードリーダーを購入しましょう。

筆者はソニーのPaSoRi(パソリ)にお世話になっています
【選び方のポイント】
・RC-S300が新しいシリーズ(RC-S380より対応OSの種類が多い)
・RC-S380/SやRC-S300/S(Sの字が付いているもの)は「法人向け」(特徴:対応OSの種類がさらに多い)
・無印やPの字が付いているものは「個人向け」
・Windowsで使うなら「個人向け」でOK(macOS対応はRC-300シリーズかRC-380/S)
パソリは、非接触型(カードを乗せるだけ)のタイプです。付属のUSBケーブルを使って、パソコンと本体を繋いで使います。
以下、PaSoRiを使って確定申告をするための手順になります。
付属品のUSBケーブルでつなぎます
提出方法の選択では「ICカードリーダライタを使用してe-Tax」を選びます
マイナポータルアプリをダウンロードします
例:Chromeの場合:国税庁の画面からインストール→自動的にマイナポータルのWebストアに移動→「Chromeに追加」ボタンを押す→「拡張機能を追加」を押すと完了
パソコン画面に「マイナンバーカードを読み取ります」などの指示がでたら、PaSoRiにマイナンバーカードを載せます
付属のクリップでPaSoRiとカードを挟むと固定できます
マイナンバーカードの暗証番号の入力画面に切り替わるので、4桁の数字を入力します
読み取りが完了すれば画面が確定申告の画面に切り替わり、入力作業をおこなうことができます
最後にマイナンバーカードの読み取りがもう一回必要になるので、マイナンバーカードだけ大切にしまったらPaSoRiはそのまま繋いでおきましょう
確定申告書の作成が終わり、確定申告書作成コーナーから電子申告をするタイミングでもう一度マイナンバーカードの読み取りを行います

筆者の感覚では、カードを載せてから番号入力後の読み取りが終わるまで(STEP4~6)の間は10秒前後ですノーストレスで3年以上使えています
PaSoRiは交通系ICカードの履歴・残高も読み取れます。事業で公共交通機関を使っている人の旅費交通費の計上や、通院費を集計して医療費控除に加算したい人の確定申告に役立ちます。
まとめ
ID・パスワード方式でできないことやデメリットを解説しました。
現在ID・パスワード方式を使っている人やこれからe-Taxで確定申告を始めたい人は、ぜひ参考にしてください。