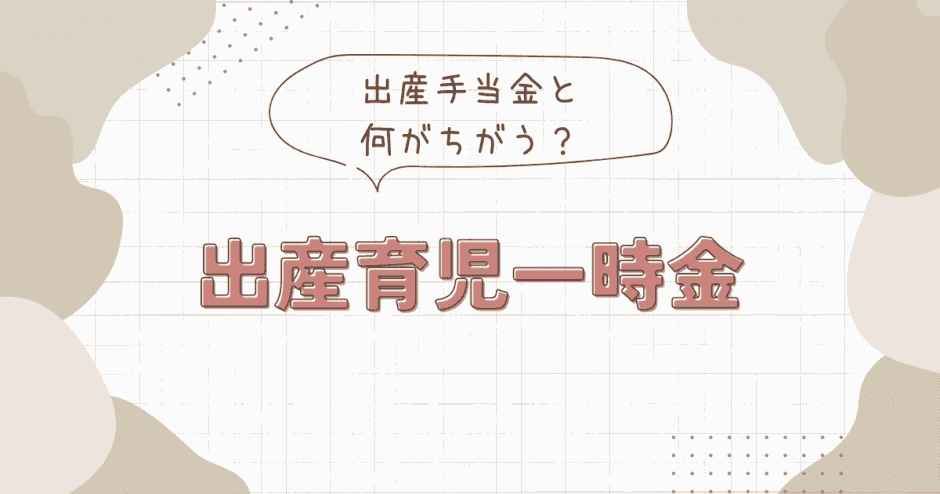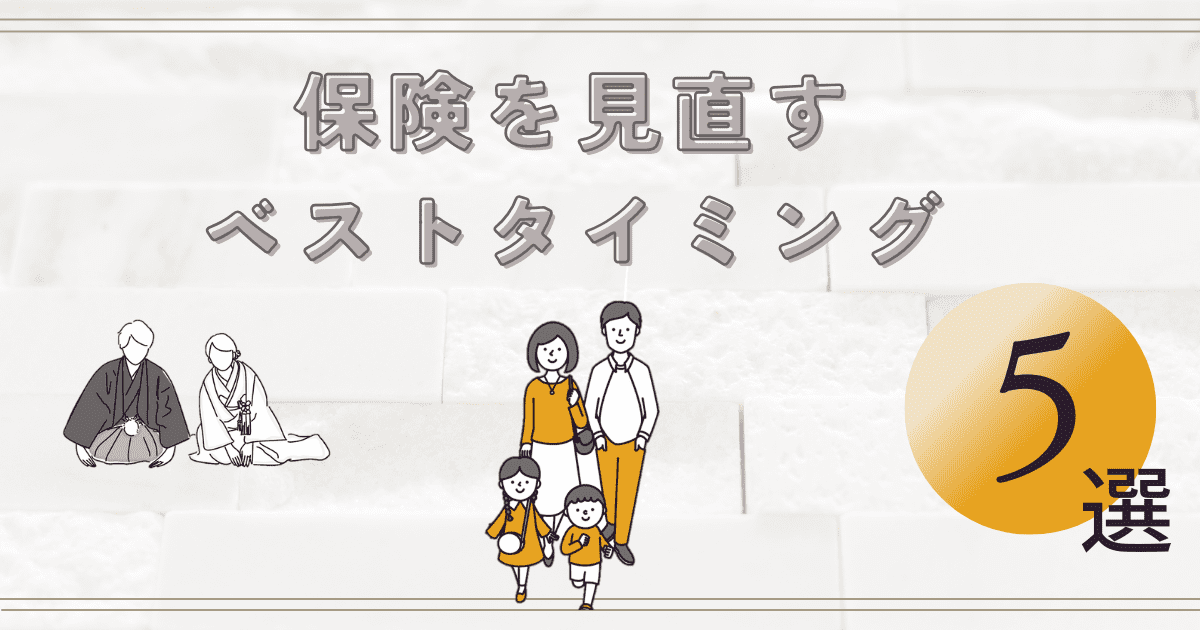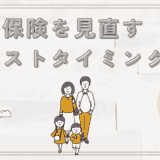出産における代表的な公的支援となる、出産育児一時金と出産手当金について、それぞれの特徴、もらえる金額などの違いを解説します。
出産育児一時金とは
出産育児一時金とは、子どもが生まれた時に公的保険から支給される一時金のことです。
出産に関係して発生するさまざまな費用に充てることができます。
支給対象者
会社員が加入する健康保険の加入者本人やその被扶養者が出産した時に支給されます。
自営業者など、市町村の国民健康保険の加入者であれば、国民健康保険から支給されます。

扶養に入っていてもいいし、自分で何らかの健康保険制度に加入していてもいいのね
出産する人が他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから6か月以内の出産の場合は、前の健康保険から支給される場合があります。

妊娠して仕事をやめた場合、やめる前に加入していた会社の保険から支給されることもあるんだね
支給される金額
支給金額は、1児につき基本的に50万円です。
かつては42万円でしたが、2023年4月から増額改訂されています。
金額は「1児につき」ですので、例えば双生児なら2人分支給されます。
なお、出産育児一時金の金額は、出産をした医療機関が「産科医療補償制度」に加入しているかどうかで若干変わります。
| 産科医療補償制度への加入の有無 | 支給される金額 |
|---|---|
| 加入している医療機関での出産 | 1児につき50万円 |
| 未加入の医療機関での出産 | 1児につき48.8万円 |
(参考)産科医療補償制度の加入について
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひの補償や産科医療の質の向上を図るための制度です。
(公財)日本医療機能評価機構のホームページで加入済みの医療機関を検索することができます。
出産育児一時金を受け取るには
出産育児一時金を受け取るには、出産した日の翌日から2年以内に、保険者(例:職場や市町村など)に申請する必要があります。
出産手当金とは
出産手当金とは、出産のために仕事を休んだ場合に、出産の日以前42日と出産日後56日までの範囲内で、その人の平均的な収入の3分の2相当が支給される制度です。
支給対象者
会社の健康保険に加入している本人が出産した場合に支給されます。
国民健康保険からは支給されませんので、例えば、自営業やフリーランスなどとして働いており家族の扶養に入っていない女性や、会社を退職した女性には原則的には支給されません。
例外として、退職までに1年以上の保険加入期間があり、かつ、退職日に出産手当金の受給要件を満たしていた場合は支給対象になります。

協会けんぽのWebサイトの下のほうに退職日に出勤したときは退職日の翌日以降の出産手当金は支払われないって書かれているから、退職予定の人は注意してね!
支給される金額
その人の1日あたりの平均的な収入の3分の2に相当する金額が、出産の日以前42日と出産日後56日のうち、仕事を休んだ日数分で支給されます。
1日あたりの平均的な収入の3分の2に相当する金額(=1日あたりの支給額)は、下記の方法で計算されます。
過去12か月間の標準報酬月額÷30日×3分の2
標準報酬月額とは:会社員の社会保険料を算定するために用いる、1~50等級に区分された給与の平均月額です。原則、毎年4月~6月の3か月間の給与をベースに年1回見直されています。
出産手当金を受け取るには
出産手当金を受け取るには、出産のために仕事を休んだ日の翌日から2年以内に保険者(会社など)に申請する必要があります。出産の日以前42日~出産日後56日の各日において、権利の時効消滅の判定がおこなわれます。
出産育児一時金と出産手当金の3つの違い
支給対象の違い
出産育児一時金は、出産にともなう様々な費用に充てるための給付です。出産をする本人が会社の健康保険や市町村の国民健康保険などに加入している場合はもちろん、家族の扶養者として加入している場合も支給対象になります。
これに対し、出産手当金は、出産によって仕事を休む女性の収入を補てんするための給付です。そのため、出産をする本人が会社などの健康保険に加入していなければ支給されません。家族の扶養として加入していても支給されないということです。
ただし、前述のとおり、退職後も一定要件を満たしていれば支給される場合があります。
支給金額の違い
出産育児一時金は支給額が決まっている一時金です。
これに対して出産手当金は、受け取る人の給与の額と仕事を休んだ期間に応じて金額が変動します。
税務上の違い
出産育児一時金と出産手当金はどちらも個人の所得にあたらず、所得税等は非課税となります。
出産育児一時金や出産手当金の支給を定めている健康保険法において、非課税となることが定められているからです。
健康保険法第62条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
ただし、出産関係の医療費について「医療費控除」の確定申告をする場合、出産育児一時金については、医療費から差し引いて申告する必要があります。
医療費控除とは、1年間に負担した医療費に基づいて計算した一定額を所得から控除できる制度です。
確定申告によって適用することができます。
医療費控除の対象となる「医療費」には、出産関係の費用も含まれます。
例えば、出産前の定期健診にかかる費用、出産前後の通院費や通院費、入院中に病院が用意する食事代など医療機関に支払う費用が代表例となります。
また、通院のためのバス代や電車代、公共交通手段の利用が困難なために使用したタクシー代なども医療費として医療費控除の対象になります。これらは医療を受けるために直接必要な費用だからです。

自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外なんだね…
ただし、出産育児一時金を受け取った場合、この出産関係の医療費からその金額を差し引かなければなりません。
医療費控除の計算では、その医療費を補てんする給付をもらった場合、それを除いて申告しなければならないというルールがあるからです。
このルールによって、出産育児一時金の他にも民間の医療保険などから受け取った入院日額や手術給付金などがあれば、医療機関に対して支払った入院費、手術費からそれぞれ差し引く必要があります。
これに対して、出産手当金は働けない期間の収入に対する給付であるため、医療費を補てんする性格のものではありません。そのため、医療費から差し引く必要はありません。