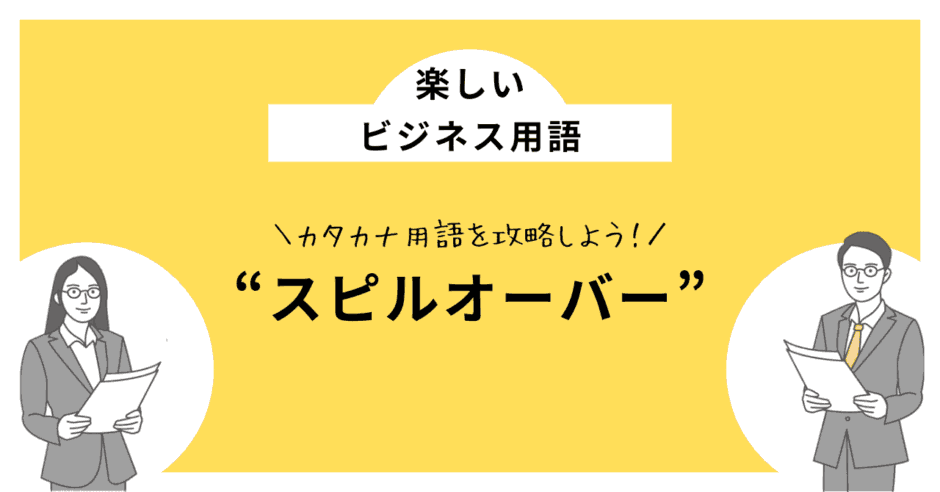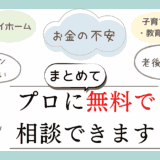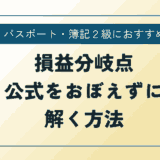スピルオーバーの意味
「スピルオーバー」とは、溢れ出ること、余波、波及などの意味をもつ英単語「spillover」から生まれたカタカナ語です。
英語の用例としては、「spillover effects」で「波及効果」、「spillover population」で「人口過剰」、「dam spillover」で「ダムの越流」などがあります。
物理的に広がって溢れていくことや、元の狙いよりも広範囲に効果が及ぶこと、思わぬ別の効果が生じることなどの現象を表す言葉であり、良い意味、悪い意味のどちらでも使われます。
ビジネス用語におけるスピルオーバー
ビジネス用語では、ある取り組みがもたらす周囲への波及効果や副次効果として「スピルオーバー」や「スピルオーバー効果」という言葉が用いられます。
良い意味の場合、例えば、自社製品の研究開発のための投資を行う場合、実施した企業だけでなく、外部企業の技術や生産性を向上させる影響が生まれることがあります。
こうした波及効果や副次的な影響を「スピルオーバー」、「スピルオーバー効果」と呼ぶことがあります。
「R&Dによるスピルオーバー効果」と言われたら、「研究開発(Research and Development:R&D)による波及効果」と訳すとよいでしょう。
なお、上記は民間投資の例ですが、公共投資(例:道路などのインフラ整備事業など)による経済効果の波及について語るときも、スピルオーバー効果という言葉が用いられます。
スピルオーバーの負の側面
前述のとおり、民間企業が、自社の製品やサービスの研究や開発に投資して成功した場合、周りの企業がその恩恵にあずかって良くなることも「スピルオーバー効果」の一つです。
このスピルオーバーは、消費者目線でみれば好ましい現象ですし、日本の国際競争力を高める観点からも、社会全体にとって良い影響だといえます。
一方で、投資を行った個々の企業にとっては、負の側面もあります。
自社が身銭を切って行った投資は、成果が生まれるかわからないリスクを抱えています。そのリスクを取ったのに、成功したら他の企業にタダ乗りされて、せっかく開拓した市場を侵食されてしまう恐れがあるのです。自社の投資が他企業にフリーライドされてしまうことで、まさに「骨折り損のくたびれ儲け」となるリスクがあります。
このように民間投資で生まれたスピルオーバー効果には負の側面もあり、このことが企業のイノベーションを妨げる要因の一つであるという見方もあります。
経済産業省は、税制改正の資料の中で、研究開発投資は成果が生まれてもフリーライドされてしまうという公共財的な性格を有しており、十分な投資が行われにくい性質があることを指摘しています。
こうしたリスクを軽減するため、政府は、研究開発投資を行う企業に対して優遇税制や補助金などの支援策を整備し、イノベーションを促進しています。