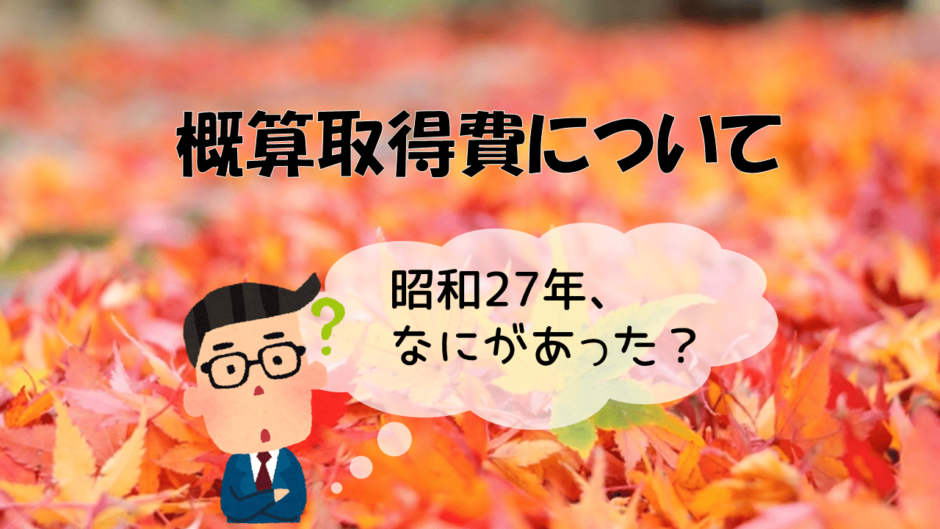インターネットで検索すれば大体のことはわかる時代になりました。しかし、検索のアルゴリズムが優秀になりすぎていて、逆にかゆいところに手が届かないケースも極まれに発生します。
所得税の「総合課税の譲渡所得」の計算において概算取得費(収入金額×5%)を適用できる「法的根拠」が、筆者にとってそのケースの一つです。
インターネットで検索すると土地や建物を売却した時の「分離課税の譲渡所得」の説明ページはたくさんあるのに「総合課税の譲渡所得」についてはなかなか答えが見つけられません。
自分の記憶力をまるで信じていない筆者は、不安になっていつも本棚を漁ってしまいます。
そして、本のページを開くと、該当する箇所には既にマーカーが引いてあって、きたない字でメモ書きがあります。もちろん自分でやったものです。忘れているのです。今日もまた、執筆の調査のためにページを開いてしまいました。
あまりに情けないので、今日こそは備忘録としてブログに残したいと思います。
譲渡所得における総合課税・分離課税の違い
譲渡所得は売却対象によって総合課税・分離課税に分かれる
所得税における「譲渡所得」とは、個人の所有物の売却益にあたる所得です。
売却する対象物が、「土地建物等や株式等」であるか「それ以外」であるかによって所得税(と住民税)の課税方法が異なります。
土地建物等や株式等の売却益は分離課税の譲渡所得に、それ以外の売却益は総合課税の譲渡所得になります。
総合課税であれば、給与や自営業の収入など経常的な所得と合算して累進課税(所得の多い人ほど税負担が重くなる課税方法)が適用されますが、分離課税であれば他の所得から分離され、それ単体で課税されるため、売却年に税負担が集中しすぎないという特徴があります。
ざっくりしたイメージでは「不動産や一部の金融資産」が分離課税、「それ以外の物(動産や無形固定資産)」が総合課税となります。
つまり、譲渡所得は売却する対象物の違いによって、分離課税と総合課税の大きく2つに分かれます。
分離課税と総合課税では計算方法について定めた条文が違いますし、条文が所在する法律も別になっています。
この記事でわかること
この記事で解説することは、「総合課税の譲渡所得」の計算において「概算取得費」を適用できる「法的根拠」です。
結論からいうと、総合課税・分離課税のいずれの譲渡所得の計算においても、概算取得費を使うことができます。
ではなぜこのようなニッチなテーマで記事を書くのかというと、総合課税の譲渡所得に概算取得費が使えるかどうかの根拠を解説した記事が、インターネットではどうにも見つからないためです。
土地や建物を売却したときの「分離課税の譲渡所得」に概算取得費を使えることは、国税庁のタックスアンサーをはじめ様々な記事で解説されています。
その一方で概算取得費を「総合課税の譲渡所得」にも使える法的根拠を説明した記事はなかなか見つかりません。
不動産を売却したときの、分離課税の譲渡所得の記事に埋もれてしまってるような印象を受けます。
しかし、物書きや資料づくりなどをされる方にとっては「国税庁のタックスアンサーでさえ触れられていないなら、自分が勘違いしていたのでは…?」と不安になって、本を引っぱり出し、根拠となる法令を探してしまうことがあるかと思います。
そうした方が、インターネットでも自身の目で法的根拠を確かめられるように、この記事で総合課税の譲渡所得の計算においても概算取得費を使える根拠を説明したいと思います。
総合課税の譲渡所得とは
まずは総合課税の譲渡所得のについての基本事項をまとめます。
対象となる売却資産の範囲
総合課税の譲渡所得の対象となる資産は、機械装置、車両、工具器具備品、鉱業権、漁業権、著作権、特許権、ゴルフ会員権、書画・骨とう品、金地金、宝石などです。
販売業や製造業における商品・製品や、消耗品のストックである貯蔵品など「棚卸資産」にあたるものは対象外になります。
総合課税の譲渡所得の計算方法
総合課税の譲渡所得は、収入金額(売却金額)から、取得費・譲渡費用・特別控除を差し引いて計算します。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(最大50万円)
短期と長期の譲渡所得がある年における特別控除50万円は、短期の譲渡所得から優先して控除することになっており、納税者にとって有利になっています。
総合課税の譲渡所得における短期・長期の判定方法
総合課税の譲渡所得における短期・長期の判定は「取得日から譲渡日まで」の期間が5年を超えるかどうかで判定されます。
「土地建物等」の分離課税の譲渡所得のように「取得日から譲渡した年の1月1日まで」ではありません。
その年の譲渡所得が、総合課税の「長期譲渡所得」に該当する場合、その金額を損益通算の後に2分の1にした金額が、合計所得金額に算入されます。
長く保有したほうが有利になる点においては、総合課税も、土地建物等の分離課税も同じということです。
なお、総合課税の譲渡所得の対象になる著作権など一部の権利については、所有期間が5年以下でも「長期譲渡所得」に該当するものがあります。
総合課税の譲渡所得における「取得費」と「概算取得費」
総合課税の譲渡所得の計算において、収入金額(売却金額)から差し引くことができる「取得費」と、その代わりとなる「概算取得費」について解説します。
取得費とは
取得費とは、売却した資産を買ったときの費用のことです。
計算方法は、売却する対象物が減価償却資産にあたるかどうかで変わります。
書画・骨とう品などの美術工芸品や、貴金属や宝石などは減価償却資産にあたりません。
その場合、取得費は下記の方法で計算します。
資産の取得に要した金額(取得価額)+設備費+改良費
設備費や改良費がなじまない物が多いと思いますので、購入費+購入手数料と考えると良いでしょう。
売却対象が、器具備品などのように減価償却の対象になる場合、取得費から償却相当額を控除します。
その場合の計算式は下記のようになります。
資産の取得価額+設備費+改良費-償却費相当額
償却費相当額とは、売却した資産が事業用資産であれば、減価償却費の金額です。
非事業用資産であれば、減価償却費の計算をする際の耐用年数を1.5倍、取得価額を0.9倍で行い、取得価額の95%を上限に計算します。
概算取得費とは
「概算取得費」とは譲渡所得の計算において、「取得費」の代わりに収入金額(売却代金)から差し引くことができる、概算の費用のことをいいます。
本来なら収入金額から差し引くべきものは、売却資産を取得した費用の実額です。
ただし、対象物が古いなどの理由から、この費用が判然としない場合があります。
そうした時に概算取得費(収入金額×5%)を取得費の代わりに計上できることによって、手間なく譲渡所得を計算することが可能となります。
とは言え、たったの5%ですから、概算取得費の他に差し引くことができるものがなければ、収入金額の95%近くが所得税の課税対象になってしまうデメリットもあります。
取得費の実額を調べることができればそれに越したことはないのですが、それを調べる手間と支払う税金を比べて賢く使い分けることがベストです。
なお、売却対象の取得価額が判明している場合であっても、「収入金額×5%」で計算したほうが有利であれば、概算取得費を取得費の代わりに使うことができます。
概算取得費と譲渡費用は併用できる
概算取得費はあくまで取得費の代替ですので、概算取得費(収入金額×5%)で取得費を計算していても、譲渡費用はそれとは別に計上することができます。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(最大50万円)
このことは、総合課税の譲渡所得も、土地建物等の売却による分離課税の譲渡所得も共通です。
概算取得費で償却相当額の計算が不要に
概算取得費を使って譲渡所得を計算する場合、償却費相当額を差し引く必要はありません。
言い換えれば、概算取得費を使うことによって償却費相当額の計算をせずに譲渡所得を計算できるということです。
総合課税の譲渡所得に「概算取得費」の使用を認める根拠
それでは、総合課税の譲渡所得に概算取得費を適用できる根拠を説明していきます。
根拠は所得税法基本通達のみ
総合課税の譲渡所得における概算取得費の規定は、法令では定められておらず、国税庁の通達で認められているのみとなります。
通達の内容は、下記のとおりです。
【土地建物等以外の資産の取得費】
”土地建物等以外の資産(中略)を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、法第38条及び第61条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、当該収入金額の 100分の5に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(以下略)”
通達の文中にある「法第38条」とは所得税法第38条のことです。その内容は、「譲渡所得の取得費を『取得に要した費用+設備費+改良費(-償却費相当額)』で計算しますよ」というものになります。前項の「取得費とは」の内容です。
もう一つの「第61条」とは所得税法第61条のことです。その内容は、「昭和27年12月31日以前から所有している資産」にかかる取得費の特例を定めたものになります。70年以上も前から所有している資産の特例です。
この特例に該当する資産を売却した場合、次の①~③のうちもっとも多い金額に「昭和28年1月1日以後に支出した設備費と改良費」を加算した額を取得費とする、と定められています。
・①:昭和28年1月1日時点の相続税評価額
・②:資産再評価法による再評価額
・③:取得価額+昭和27年12月31日以前に支出した設備費と改良費
総合課税と分離課税のニュアンスの違い
土地建物等の売却による分離課税の譲渡所得において概算取得費の適用を認める根拠は、「租税特別措置法」と「通達」に分かれています。
まず、租税特別措置法の条文では、昭和27年12月31日以前から所有している土地建物等について、①概算取得費(収入金額×5%)か②本来の取得費のどちらか高い金額を取得費にすることが定められています。
これは「本来の取得費もきっちり調べて比較せよ」ということではなく、あくまで「①が原則ですが、②のほうが高いとあなたが証明できるなら②にしていいですよ」という文面で定められています。
では、昭和28年1月1日以降に取得した資産はどうなのかというと、「租税特別措置法基本通達」において、このルールを引き続き使って計算して差し支えないこと(=概算取得費を使ってもよいこと)が定められています。
租税特別措置法の条文と、通達の本文を紹介します。
【長期譲渡所得の概算取得費控除】
”個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額”
(租税特別措置法第31条の4第1項)
出典:e-Gov法令検索
【昭和28年以後に取得した資産についての適用】
”措置法第31条の4第1項の規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の譲渡所得の金額の計算につき適用されるのであるが、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費についても、同項の規定に準じて計算して差し支えないものとする。”
昭和27年以前から取得している資産について概算取得費の根拠を比較してみると、総合課税と分離課税によって、そのニュアンスに若干の違いがみられます。
総合課税の譲渡所得の場合、「原則は本来の取得費だけど、概算取得費で計算したのならそれでいいよ」というゆるい感じです。
これに対して、土地建物等による分離課税の譲渡所得では「原則は概算取得費だけど、本来の取得費がそれより大きいと証明できるならそっちにして」とし、金額の大きい方を選ぶことを求めています。原則がどちらにあるのかについても、文面上は逆になっていますね。
しかし、どちらの概算取得費についても、本来の取得費が判明しない場合にはもちろん、両方わかる場合は納税者にとって有利なほうを選ぶことができる点は同じです。大した違いはありません。
昭和27年に一体何があった?
前述のとおり、所得税法第61条では、昭和27年12月31日以前から所有する資産の売却について、その取得費を、昭和28年1月1日時点の「相続税評価額」などのうちもっとも高い額で算定できるようになっています。
相続税評価額といえば、相続税の計算に使う財産の時価のことです。
なぜ所得税の譲渡所得の話に、相続税の話がでてくるのでしょうか。
そして、なぜ「昭和27年12月31日以前」を境に取得費を区別するようになったのでしょうか。
昭和27年といえば1952年ですから、今から70年以上も前のことになります。
最近は財務省のホームページにおいて各年の税制改正についての資料がわかりやすく並べられていますが、さすがに70年以上も前の資料はそうはなっていません。そこで、国立国会図書館が運営する「国会議事録検索システム」から昭和27年における国会議事録を飛ばし飛ばしに読んでみたところ、この時代における税制の混乱の様子を少しばかり感じ取ることができました。
昭和27年当時は、戦後のシャウプ勧告による新しい税制がスタートして間もない年になります。
新しい税制によって生じたさまざまな問題が当時の国会で議論されているのですが、その中で2つ、譲渡所得に関係のありそうな制度を見付けました。
1つは、当時の相続の制度です。
現行の税制では、相続で取得した資産には時価で相続税が課され、後にその資産を相続人が売却した場合は、被相続人から承継した取得費で譲渡所得が計算されるしくみになっています。時価に1回、キャピタルゲインに1回ずつ課税されるわけですが、そのタイミングが、相続時と売却時で別々の時期に分散されています。
ところが昭和27年当時は、昭和25年度の改正によって、相続発生時に「所得税→相続税」の順番で2つの課税を同時に行うことにしていたようです。
相続発生時にまず遺産を時価で相続人に譲渡したものとみなして「譲渡所得税」を課税し、その残りに「相続税」を課税していたことが、当時の国会の発言記録から読み取れます。
”昭和二十五年度の改正で相続が開始しました場合におきましては、先ずそのときの時価で評価しまして、譲渡したものと見なしまして譲渡所得税を課税し、その残りにその相続税を課税することにいたしたのであります。”
出典:国会議事録検索システム(国立国会図書館)「第13回国会参議院大蔵委員会第14号昭和27年2月15日」会議録本文における大蔵省主税局長平田敬一郎氏の発言内容を一部抜粋したもの
ところが「これでは納税が困難だ」ということになり、上記の発言は「この税制はやっぱり廃止しようと思う」という政府の意見にそのまま続きます。廃止されるまでの期間は、たったの2年だったようです。
その半月後の国会において、出席委員の一人が、この2年間の相続人に対して「非常にお気の毒」と発言した記録があります。世間では阿鼻叫喚・不満爆発の税制だったのではないかと思うのですが、近代文学小説のような文体も相まって、とてもシュールな印象を受けます。
”税法に深い伝統のある英国や米国ですら、課税されていないのにかかわらず、日本の、しかも伝統的に長子の家督相続の習慣の強い日本において、このみなし譲渡所得税をかけるということは、いかに学者的理想を追つたとはいえ、あまりに現実無視であつたのであります。今からでもおそくはない。政府が一挙にここに改正せられるということは、まことにけつこうに考えるのであります。しかし過去二年間にわたつて相続せられた方方、特に山林等の所得者であつた方々が、現行税法によつて、一度の相続でもつて税を払うために、所有の山の立木をほとんどまつ裸に売り払つて納税させられた、そういう方々に対しては、今非常にお気の毒であつたと思うのでありまして、これらがまたこの国土の緑化政策に非常な支障となつておつたということを、心から痛感しておるのであります。”
出典:国会議事録検索システム(国立国会図書館)「第13回国会参議院大蔵委員会第25号昭和27年3月1日」会議録本文における奥村又十郎委員の発言内容を一部抜粋したもの
もう1つは、インフレ対策としての「再評価税」です。
戦後のインフレによって物価が急上昇し、企業は減価償却ができず税負担に苦しんでいるという状況がありました。そこで「資産再評価法」によって資産を再評価してその価値を合理的な金額に合わせたのですが、その際、資産再評価額との差額(評価益)には6%の「再評価税」が課されました。この税は、昭和36年に廃止されています。
昭和27年12月31日以前から所有する資産を今も区別している理由は、当時の物価高騰と税制の変遷が関係しているようです。この時代の資産には相続税評価額や資産再評価額によって譲渡所得税・再評価税をすでに課されている場合があるため、おそらくこれらを次の売却において再び課税しないようにしよう(=すでに課税対象となった金額を取得費とすることによって、次の課税対象となるキャピタルゲインから控除しよう)とした配慮なのだと思います。
まとめ
総合課税の譲渡所得であっても、取得費の代わりに概算取得費を使うことができます。その根拠は、所得税法基本通達38-16です。
おつきあい下さり、ありがとうございました。