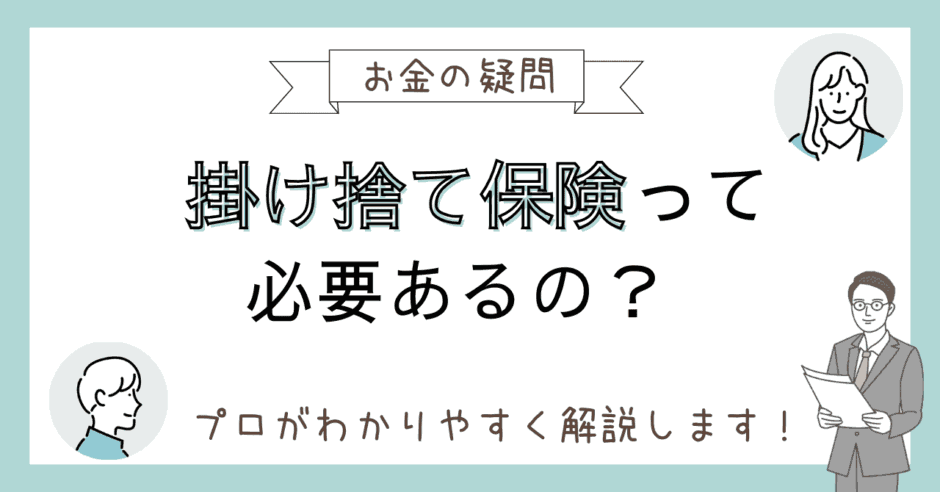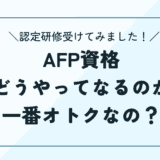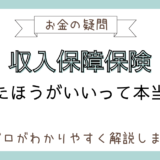ある日の昼休み、◯✕生命の販売員さんが、経理部の吉田くんを尋ねてやって来ました。


こんにちは、吉田さん
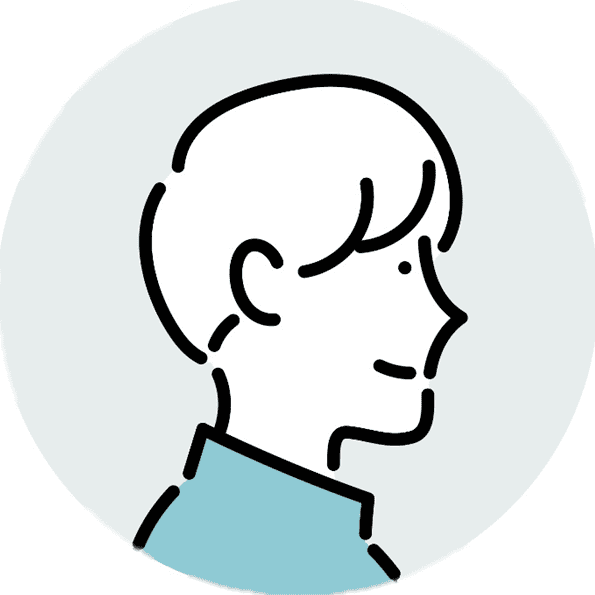
あっ◯✕生命さん!

デスクでお弁当ですか?
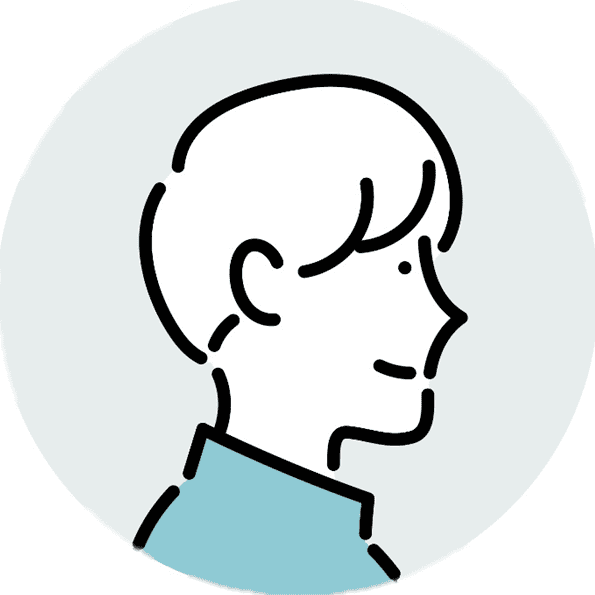
はい!手作りです!
といっても、今日はこれだけです

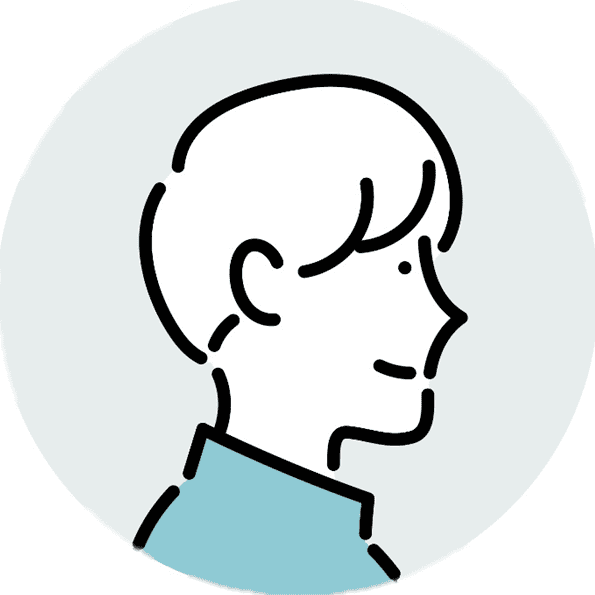
節約中なんですよ

け、健康的ですね……
ところで生命保険の契約なんですが、その後いかがですか?
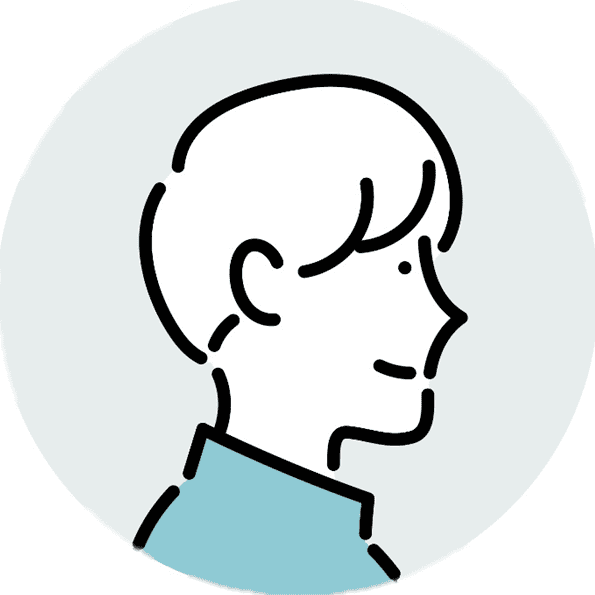
僕、今お金が無いんですよ
積立投資を始めたばかりで…

それなら、定期保険はいかがですか?
吉田さんの年齢なら、月額980円で1,000万円の保険に入れますよ
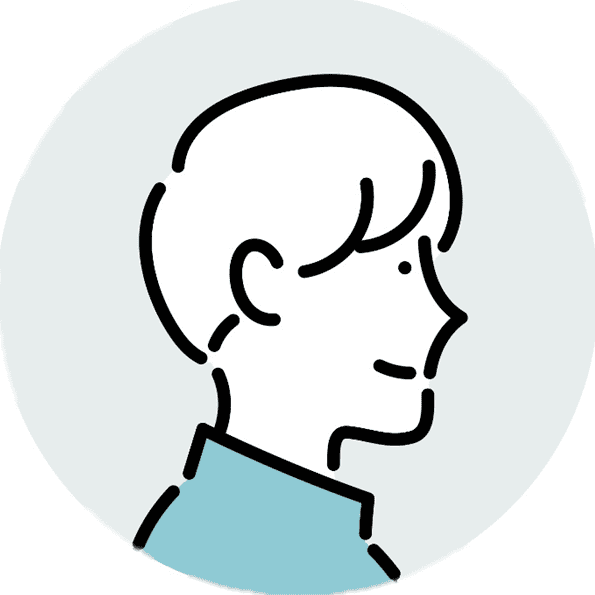
えっ安い!

吉田くん、ちょっと待って!
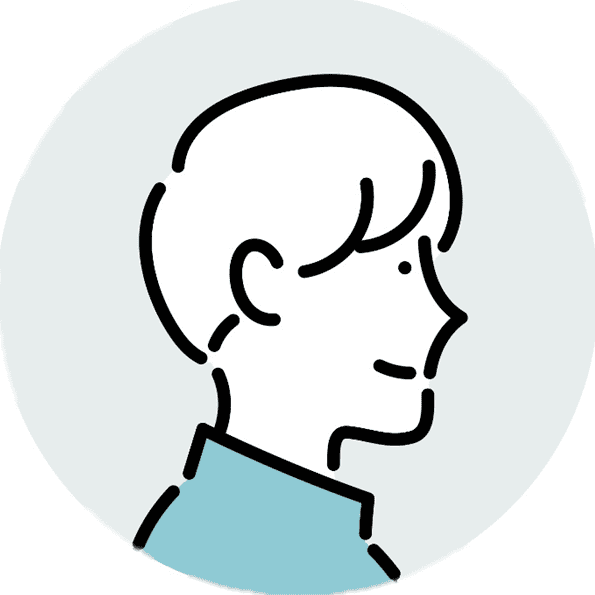
先輩!

定期保険って「掛け捨て」だよ?
解約してもお金が戻ってこないタイプなんだけど、それでいいの?
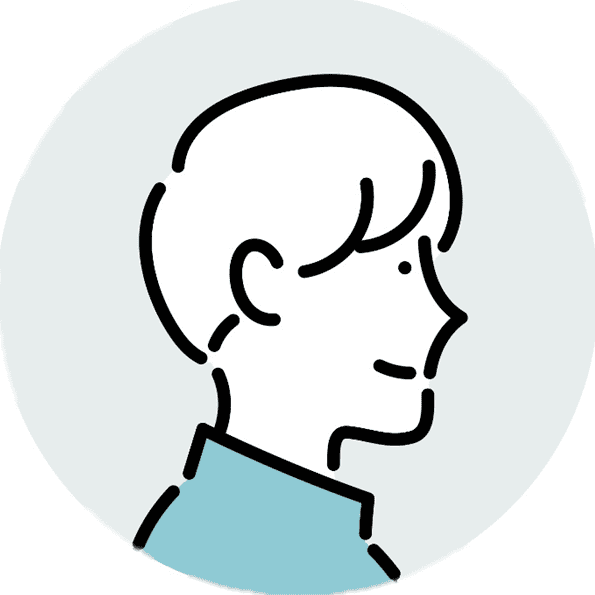
えっ逆にお金が戻ってくる保険があるんですか!?

ありますよ、でも……
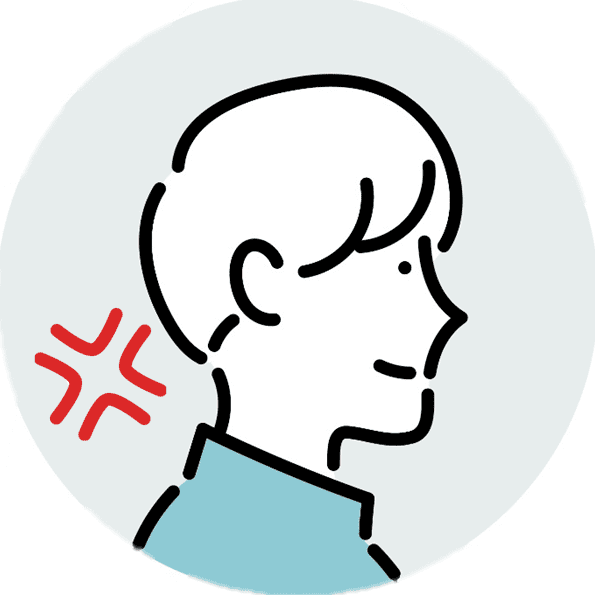
それなら、お金が戻ってくる方がいいに決まってるじゃないですか!
僕が何も知らないと思って、変なもの売りつける気ですね!

そんな…

吉田くん、定期保険はコスパ最強の保険ですよ
◯✕生命さんは吉田くんの懐事情を聞いて、この保険を勧めてくれたんです
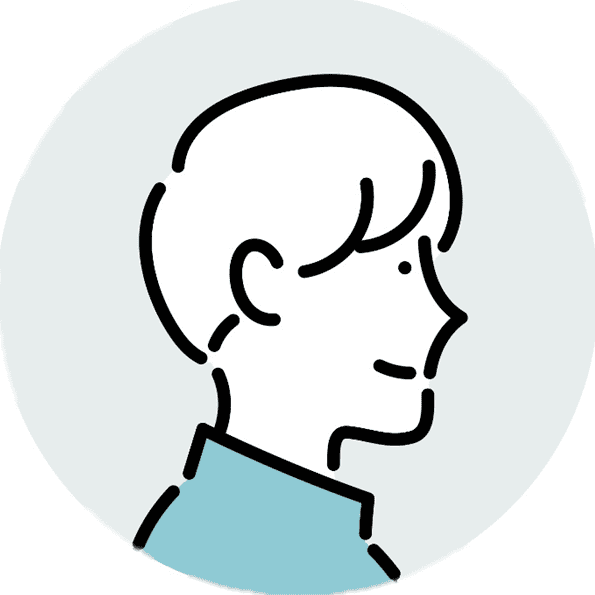
あっ主任!

でも「料金が安い」という理由だけで選ぶと、後悔するかもしれません

コスパ最強なのに、後悔??
詳しく教えてください!
・掛け捨て保険とは、生命保険の一つであり、その魅力は保険料が安いことです。
・しかし、「掛け捨てにならないタイプの保険」に比べると、お金が戻ってこないため「損をしている」と感じやすい面があります。
・さらに「料金の安さ」のみに惹かれて選ぶと失敗しやすいです。うまく活用するにはコツがあります!
この記事では、掛け捨てタイプの保険が本当に必要かどうかを、1級FPライターの筆者が中立な立場から解説します。

1級FPライター
イシダ
元・会計事務所の1級ファイナンシャル・プランニング技能士。Lancers金融ライタースペシャリスト認定。
【PR】保険選びはFPへの無料相談がおすすめ!
そもそも掛け捨て保険とは何か

掛け捨て保険とは、保険期間が満了したときの「満期保険金」や契約を解除したときの「解約返戻金」が支払われない保険をいいます。

保障が受けられる期間内に何も起こらなかった場合は、文字どおり「掛け捨て」になります
代表的な保険は、生命保険の「定期保険」です。
一生涯の保障ではなく、10年や20年などあらかじめ定められた期間のみ、死亡保障が受けられるタイプの生命保険になります。
これに対し、契約すれば保障が一生つづく保険は「終身保険」となります。

人はいつか必ず亡くなるため、終身保険が掛け捨てになることはありません
掛け捨て保険の保険料が安い理由

掛け捨て保険(定期保険)の保険料が安い理由は、2つあります。
保障に特化しているから
1つは、掛け捨て保険が保障に特化しているからです。
満期保険金や解約返戻金のあるタイプの保険(終身保険)は、「保障」と「資産形成」の2つの役割をもつため、掛け捨てにならない「お得感」がありますが、その分、保険料は高くなります。
これに対し、掛け捨て保険の役割は「保障のみ」なので、保険料を安く抑えることができます。

終身保険について補足です!
「資産形成」といっても、銀行などの預貯金とは異なり、元本割れも起こります

元本割れしにくい商品なら安定感はありますが、受け取りまでの期間が長い割に利率がしょっぱいことも……
年齢が若いから
もう1つの理由は、加入しようとする方の年齢が若いからです。
人が亡くなる確率(=死亡率)は年齢が若いほど低くなります。
掛け捨て保険(定期保険)は、この確率論で保険料を決めているため、加入しようとする方の年齢が20代~40代であれば、保険料がかなり安いのです。

20代や30代なら、月1,000円程度で加入できる掛け捨て保険も少なくありません
加入者の年齢が若いほど、保険金を支払うことなく保険期間が終了する可能性が高いため、保険会社もたくさんの保険料をもらわなくて済むのです。
掛け捨て保険を「安いから」で選んではいけない理由

「保険料が安い」という理由だけで掛け捨て保険に加入すると、後悔する可能性があります。その理由は、次の2つです。
更新のたびに保険料が上がるから
掛け捨て保険の場合、保険期間が終了した後も保障を続けるには契約の更新が必要になりますが、保険料は、更新のたびに上がります。

ずっと安い保険料が続くわけじゃないんだ……
ちなみに、掛け捨て保険の保険料はどのくらい上がるのでしょうか。
掛け捨て保険(保険期間10年、保険金1,000万円)について、20歳男性の保険料を基準に、30歳・40歳・50歳・60歳においてそれぞれ何倍になっているかを調査しました。
| 年齢 | A社 | B社 | C社 |
|---|---|---|---|
| 20歳 | 基準 | 基準 | 基準 |
| 30歳 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 |
| 40歳 | 2.1倍 | 2.0倍 | 2.1倍 |
| 50歳 | 4.5倍 | 4.3倍 | 4.6倍 |
| 60歳 | 10.3倍 | 11.0倍 | 10.6倍 |
| 70歳 | 加入不可 | 加入不可 | 28.1倍 |

40代くらいまでは安いけど、50歳で4倍、60歳で10倍くらいになるんだ……
どの保険会社も保険料の上昇率に大きな差は見られませんでした。死亡率に基づいて保険料が決まるため、当然の結果といえます。
年齢が高くなると更新できなくなるから
掛け捨て保険は、年齢が高くなると更新できなくなります。

上限となる年齢は保険会社によって異なりますが、70歳くらいが目安です

更新できなくなった後は、どうなるんですか?

生命保険に加入し続けたいのなら、保険会社によっては85歳くらいまで加入できる商品もありますので、そちらに乗り換える方法があります

「終身保険」であれば、年齢に関係なく加入できます
年齢が上がると掛け捨て保険を更新できなくなります。その場合は、①生命保険をやめる、②他社で加入できる定期保険を探す、③終身保険に新規加入する、といった選択を迫られます。
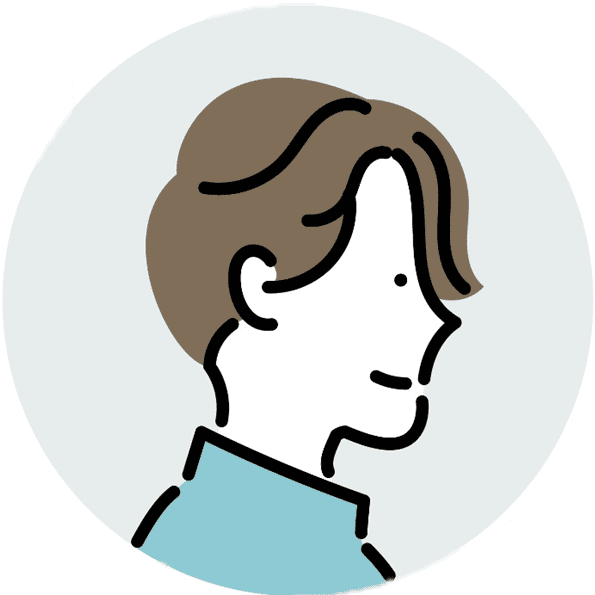
終身保険に加入するってことは、「掛け捨てにならないタイプに入り直す」ってことだよね?

そのとおりです

ただし、高齢になって加入する終身保険の保険料はかなり高額になります
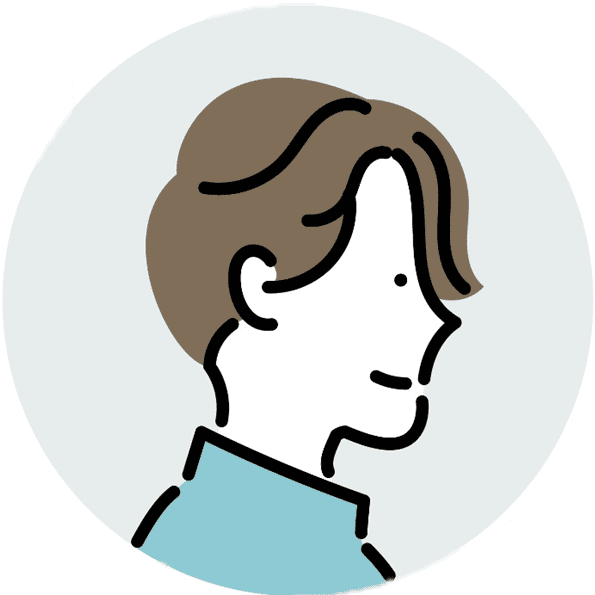
亡くなる可能性が高い年齢で加入すると、保険会社も保険料を運用する期間が短くなるわけだから、当然そうなるよね
保険会社は、支払われた保険料を金融資産などで常に運用しており、その運用益の見込み率(予定利率といいます)を保険料の割引に充ててくれる仕組みがあります。終身保険ではこの割引がとても重要なのですが、高齢になって加入すると運用期間が短い(=運用益が伸びにくい)ため、若いうちから加入する人よりも保険料が割高になるのです。
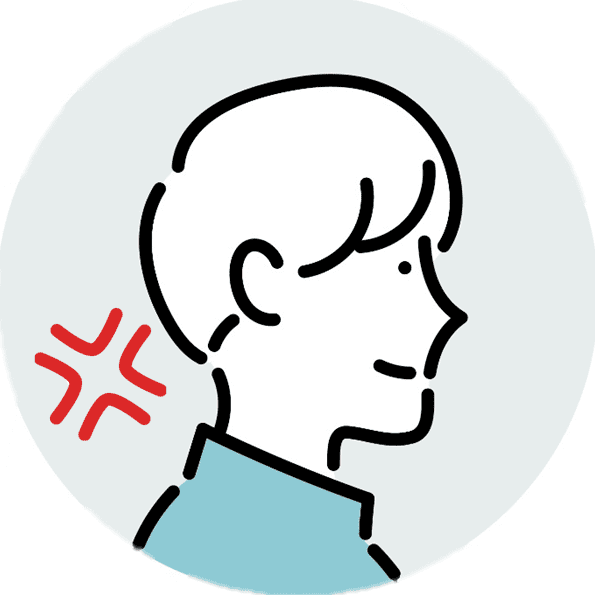
そ、そんな…
やっぱり「掛け捨て保険」なんて必要ないじゃないですか!

いえ、決してそんなことはありません
コスパ最強の定期保険の利点を活用するのです!
掛け捨て保険は本当に必要?無駄なく利用するための3つのポイント

・掛け捨て保険は、20代~40代までは、保険料が安く加入しやすい保険(20~30代なら月1,000円程度もある)
・しかし、50代や60代になると更新するたびに保険料が大きく上がる(60代は20代の10倍以上!)
・さらに、70代や80代になると、更新そのものができなくなる
・更新をやめれば、保障はその期間で終了となり、その際に受け取れる満期保険金などはない(掛け捨てとなる)
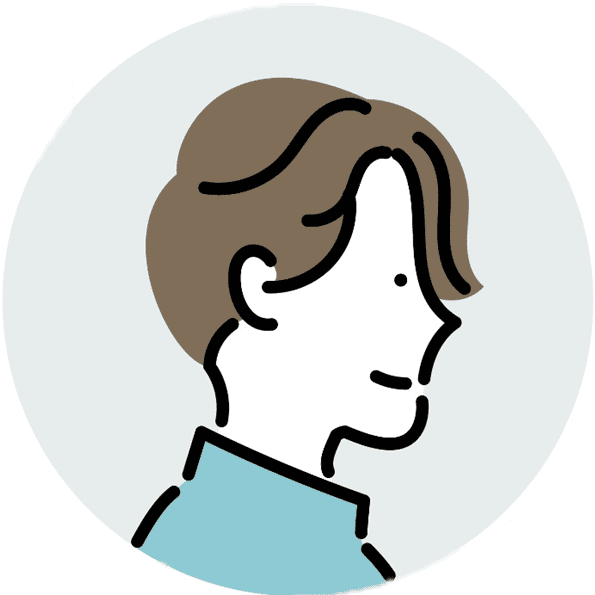
それなら僕は、最初から掛け捨てにならない「終身保険」を選ぶよ

若いうちにそれを選ぶことも、一つの選択ですね

でも、保障が必要な時期だけ利用すれば、掛け捨て保険はコスパ最強ですよ
ここからは、掛け捨て保険を無駄なく活用できるかどうかを判断するための、3つのポイントをお伝えします。
保障が必要な期間が決まっているか
1つめのポイントは、死亡保障を必要とする期間が決まっているかどうかです。
生命保険は、被保険者(死亡保障の対象者の方)が亡くなった後に、残された家族の生活を守るための保険になります。
そこで、家族構成や年齢、それぞれの収入状況などに応じて、死亡保障を必要とする期間を限定できないかどうかを考えてみましょう。

たとえば、お子さんが独立する年代までに限定して保険に入る、といった活用方法がおすすめです
・家族構成・年齢・収入などに応じて、死亡保障が必要な期間を限定してみましょう。
・保障したい期間を限定できる場合は、その間のみ掛け捨て保険(定期保険)の安い保険料で保障を受けることがおすすめです。
・20代~30代の保険料はとくに割安なので、あまったお金を、生活費、貯蓄、投資などに回しやすくなります

たとえば、保険料が大きく上がる50歳くらいまでに、お子さんに必要な残りの教育資金を貯蓄で用意できれば、保険を更新せず、そこでやめるという戦略もあるのです
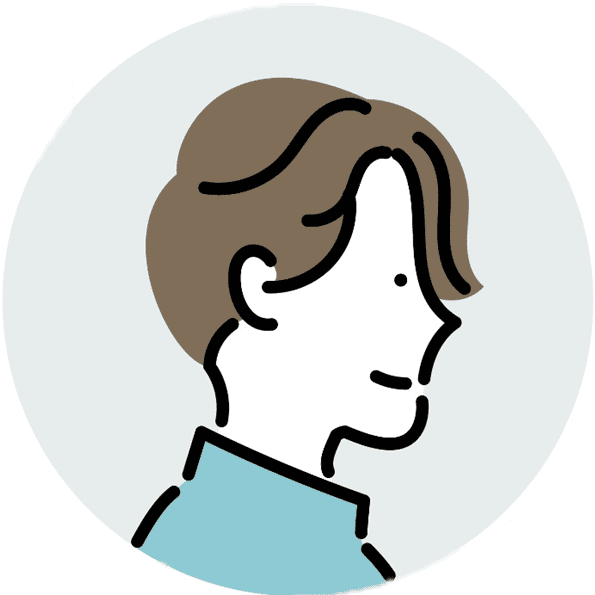
子育ての費用に備えるのなら、貯蓄の少ない若い間だけ加入すれば保険料は格安だから、かなり効率よく使えるんだね
逆に、期間を限定できない場合は、掛け捨て保険よりも終身保険を選んだほうが、先ほどの「割引率」の観点からも、生涯で支払う保険料を抑えられます。
必要な保険金額が決まっているか
2つめのポイントは、必要な保険金額が決まっているかどうかです。
掛け捨て保険に限った話ではありませんが、いくら保障が必要かを算出しておくことは、無駄のない保険選びには絶対に欠かせません。
いくら保障が必要なのか判断軸をもたないまま保険会社に相談すると、保障の大きい高額な保険を勧められる可能性があります!

最近は、保険金額を100万円単位で選べる定期保険もあるため、ムダのない保険選びのためにはかなり重要な観点となっています
・必要な保険金額を決めないまま保険を選ぼうとすると、ムダに高い保障のついた保険を選ばされがちです。
・まずは、必要な保障を見極めましょう!
・世帯の収支と貯蓄から見極める必要があります。
・まずは、現在の家計の状態と、それが続いた場合の老後の状況を知るためにライフプランを作成することが大切です。
・それにより、保険でいつまでにいくら備えておけば安心かを正しく判断できるようになります。
【PR】保険選びはFPへの無料相談がおすすめ!
保険で資産形成をする必要があるか
最後のポイントは、保険で資産形成をする必要があるかどうかです。
掛け捨てにならない保険(終身保険)は、保障に加えて資産形成の手段になる点が魅力です。
しかしその一方で、資産形成の手段は保険以外にも豊富に存在します。特に、NISAやiDeCo、勤務先の企業が導入されている退職金制度など、保険よりも税制面で優遇されたさまざまな選択肢があります。
そのため、あえて保険で「保障+資産形成」にしなくても、保障と資産形成を切り分けて、保障は掛け捨て型保険で、資産形成は他の制度のように組み合わせることもできるのです。
・終身保険を選ぶ際は、本当に保険で資産形成をする必要があるかどうかの視点も大切です。
・比較したい制度は、NISA、iDeCo、企業型DC(マッチング拠出など)になります。

吉田くんは、積立投資を始めたんですよね?

そうなんです!
NISAではじめました!将来のためにと思って!

でしたら、保険は「保障の機能のみ」でいいのではないでしょうか
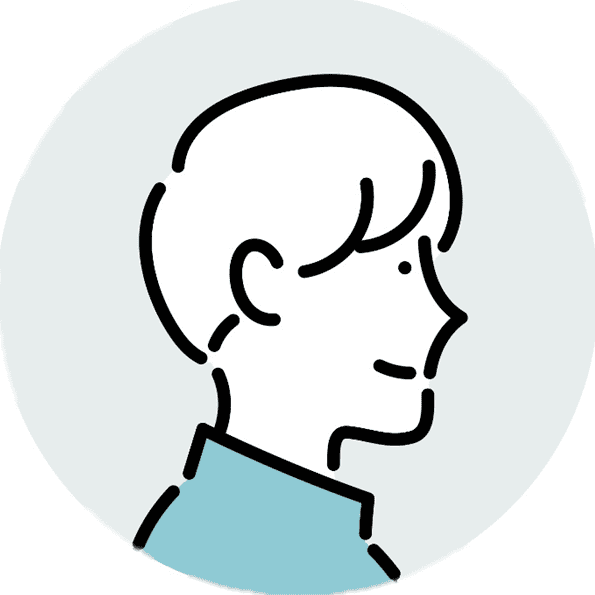
でも掛け捨てにならない保険も気になります……
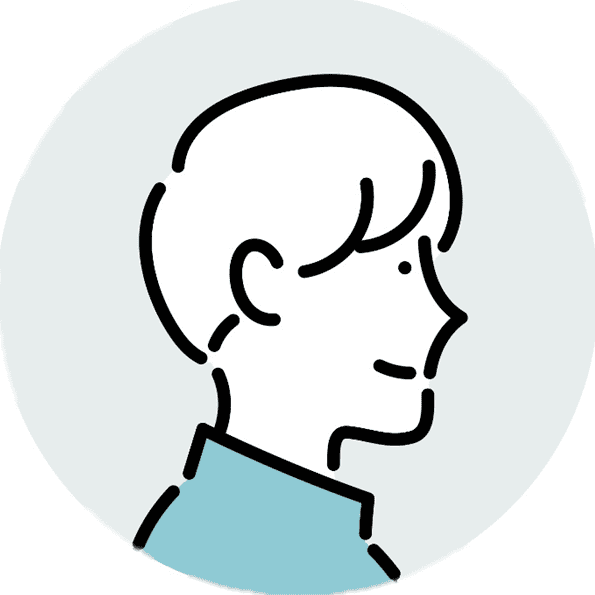
たぶん僕って、自分の将来の計画がちゃんと立てられている自信がないから、いろんなところで迷うんでしょうね……

そういう時はFPの無料相談を利用するんですよ!
【PR】保険選びはプロの無料相談を活用しよう

・掛け捨て保険をムダなく活用するには、必要な保障を、ご自身や家族の状態から見極めることが不可欠です。
・必要のない保険を選ばないようにするには、現在の家計の状態から将来を知ることが欠かせません。

自分にもっとも合う保険をムダなく選ぶなら、お金のプロによる無料相談を利用しましょう!
おすすめの無料相談
・4,500名以上のFPと提携
・相談しやすいFPとマッチング
(合わない時のためのイエローカード制)
・満足度95%!
・公式サイトにお客様の声を多数掲載!

公式サイトには利用者の声も掲載されているんですね!

保険選びは、目的をしっかり定めてそれに必要な分だけ加入することがもっとも効率的です
わからないことは、プロに相談して解決しましょう!